佐野市飛駒町・戸室・船越・岩崎の神社資料

主祭神:天児屋根命・大己貴命・少彦名命 配神:市杵嶋姫命・水波之女命(罔象女神) 境内社:西宮大神宮・稲荷神社・天満宮・根本神社
『栃木県神社誌』平成18年版では天文十一年1542創立としているが『下野神社沿革誌』は治承年間1177~81駒寄正八幡宮として創建としている。また「飛駒」「閑馬」の由来も記している。天文十一年1542駒形大明神と改称。明治六年1873駒形神社とす。
大正三年1914四月,字中木戸川西の山神社,字出川の水神社,字多高の阿夫利神社,十月字坂本の厳島神社を合祀。
例祭:10月15日
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
安蘇郡 正一位 駒方大明神 上彦間 神山伊賀
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-35丁
飛駒村大字上彥間小字宮原鎭座 村社 駒形神社 祭神天兒屋根命 大己貴命 少彥名命 祭日大四月十五日小九月十五日 氏子五百十八戸總代七員 社掌藤倉若丸同村大字入彥間四二三番地住小野誠一郎同村大字上彥間二三一番地住神山信吉同村大字同二一三番地住
本村は舊麻郡/今安蘇郡と改む/佐野庄に編して遠原の郷と呼びしか后ち上下に分かれて上遠原と稱せらる 其頃は草より出てゝ草に入る月の武藏野ならなくに只た茫々たる山野にして頗る野馬を蕃息せり 時に治承年間1177~81二頭の良馬出づ一は土人上遠原の中央なる毛野山の麓に獲一は脱して下遠原に至り止る遂に二つながら之を擒へて源賴朝に献ず 即池月磨墨にして共に公か秘藏の逸物とはなれり 故を以て上遠原を飛駒村に下遠原を閑馬村に改め產土神を駒寄正八幡宮と稱して創立せしもの即ち本社の濫觴なりと/按するに池月磨墨の良馬も元とは野馬のことゝて悍にして馭す可からざりしならん故に其走ること飛ふことくなるを以後飛駒と改稱し叉仙の一頭は飛び出して下遠原に至り閑まりし故閑馬村と稱せし者なるぺし殊に今も木村の字に中木戸又た中木戸川などあるを以て見れば牧塲の木戸に充てたる所の名を存ずるものと想はる/其の創立の年號は詳ならさるも右の口碑に依り察するときは恐らくは七百餘年前の創設に係る古社なりしことは疑べくものあらず 其后天文十一年三月駒方大明神と改稱し降つて元録四年三月宣旨正一位を授けらる 明治六年社格改正の際改めて駒形神社と稱す 傳ふる所の由緒正に斯の如きのみ 因に云ふ元との飛駒村も后ち又上下に分ち寛永十年四月江州彥根の城主井伊候の領となるに及ひて彥根の彥を用ひて彥間と書き改ためしが明治廿一年町村制實施の際復た飛駒に改たむ
建物本社間口九尺奥行六尺小羽葺 拜殿間口三間半奥行二間半瓦葺 神樂殿間口六間奥行三間半茅葺 石華表一基 境内地千七百三坪本大字の中央平地にあり宮殿は南向きにして四方廣濶人家の點々たるを見る 前は飛駒の流水潺湲として晝夜を舎てず風籟と相和し琴瑟を聞くが如とし 境内には杉檜樫の大木あり緑り濃やかに適ま異禽の喈聲を弄するあり眞に耳目を爽やかならしむる別乾坤なり
『栃木県神社誌』平成18年版では天文十一年1542創立としているが『下野神社沿革誌』は治承年間1177~81駒寄正八幡宮として創建としている。また「飛駒」「閑馬」の由来も記している。天文十一年1542駒形大明神と改称。明治六年1873駒形神社とす。
大正三年1914四月,字中木戸川西の山神社,字出川の水神社,字多高の阿夫利神社,十月字坂本の厳島神社を合祀。
例祭:10月15日
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
安蘇郡 正一位 駒方大明神 上彦間 神山伊賀
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-35丁
飛駒村大字上彥間小字宮原鎭座 村社 駒形神社 祭神天兒屋根命 大己貴命 少彥名命 祭日大四月十五日小九月十五日 氏子五百十八戸總代七員 社掌藤倉若丸同村大字入彥間四二三番地住小野誠一郎同村大字上彥間二三一番地住神山信吉同村大字同二一三番地住
本村は舊麻郡/今安蘇郡と改む/佐野庄に編して遠原の郷と呼びしか后ち上下に分かれて上遠原と稱せらる 其頃は草より出てゝ草に入る月の武藏野ならなくに只た茫々たる山野にして頗る野馬を蕃息せり 時に治承年間1177~81二頭の良馬出づ一は土人上遠原の中央なる毛野山の麓に獲一は脱して下遠原に至り止る遂に二つながら之を擒へて源賴朝に献ず 即池月磨墨にして共に公か秘藏の逸物とはなれり 故を以て上遠原を飛駒村に下遠原を閑馬村に改め產土神を駒寄正八幡宮と稱して創立せしもの即ち本社の濫觴なりと/按するに池月磨墨の良馬も元とは野馬のことゝて悍にして馭す可からざりしならん故に其走ること飛ふことくなるを以後飛駒と改稱し叉仙の一頭は飛び出して下遠原に至り閑まりし故閑馬村と稱せし者なるぺし殊に今も木村の字に中木戸又た中木戸川などあるを以て見れば牧塲の木戸に充てたる所の名を存ずるものと想はる/其の創立の年號は詳ならさるも右の口碑に依り察するときは恐らくは七百餘年前の創設に係る古社なりしことは疑べくものあらず 其后天文十一年三月駒方大明神と改稱し降つて元録四年三月宣旨正一位を授けらる 明治六年社格改正の際改めて駒形神社と稱す 傳ふる所の由緒正に斯の如きのみ 因に云ふ元との飛駒村も后ち又上下に分ち寛永十年四月江州彥根の城主井伊候の領となるに及ひて彥根の彥を用ひて彥間と書き改ためしが明治廿一年町村制實施の際復た飛駒に改たむ
建物本社間口九尺奥行六尺小羽葺 拜殿間口三間半奥行二間半瓦葺 神樂殿間口六間奥行三間半茅葺 石華表一基 境内地千七百三坪本大字の中央平地にあり宮殿は南向きにして四方廣濶人家の點々たるを見る 前は飛駒の流水潺湲として晝夜を舎てず風籟と相和し琴瑟を聞くが如とし 境内には杉檜樫の大木あり緑り濃やかに適ま異禽の喈聲を弄するあり眞に耳目を爽やかならしむる別乾坤なり
主祭神:大山祇命 配神:薬師大神(如来)
役行者が富士山から東北を見ると瑞雲たなびく山が見えたのでやってきたのが飛駒の地,雲の根方に奇峰を見つけ根本山と名付けた。ここに天正元年1573良西が創立。桐生口と飛駒口にそれぞれ里宮の遥拝所がある。飛駒口は根古屋森林公園に,桐生口は田沼から群馬県に編入された今倉にあったらしいが,桐生川ダムに沈んだか。
例祭:5月3日登拝祭 11月15日
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-35丁
同村字根本山鎭座 無格社 根本山神社 祭神大山祇命 祭日四月二十四日十一月十五日 信徒五百十八戸總代六員 社掌藤倉若丸同村大字入彥間四二三番地住小野誠一郎同村大字上彥間二三一番地住 當社は天正元年1573四月一日先師良西行者の創立にして世襲の神地靈塲たり 舊記を按ずるに往昔役行者富士山に上ぼり東北を臨みしに瑞雲天に靆くの山あり即ち其雲を指して至れは雲の根方に古木蓊蔚として⾭苔滑かに荊棘途を埋めて怪岩地に峙つの奇峰あり故に之を根本山と名づく 後ち弘法大師東國飛錫の時登山して之れ神靈擁護の地なり後世遠近の輩群參の靈塲となるべしと云へり 果せる哉幾星霜を經て中興の法印良西桐生川の流れにしたかひ登山して相承の秘法を修し嫡々相傳ふる 二百餘年始めは信徒等參詣せんとせしに山中霹靂鳴動して咫尺を辮ぜざるか故に登山すること能はざりしが苦練修行の効空しからず遂に是の靈境を開らき信心の輩無羨に登參するを得るに到りしなりと かヽる由緒あれはにや舊領主井伊掃部頭は本社を祈願所と崇め毎歳祈禱を執行して神札を/長さ三尺檜神札/拜受するの例あり 又た高家宮原弾正大弼旗本野々山丹後守横瀬美濃守等も同じく神札を拜受して金穀物品を寄進すること其例となれり 且つ天保二年四月徳川家康公の妾歌浦殿病氣の際も當社永良印師御召を蒙むりて本丸に登城し病氣平愈の所禱をなしたる効により紫縮緬幕を寄進されたり 今ま神札に對する毎年の寄進高を列記すれば左の如くなりき 金千匹御供米二俵領主井伊侯より金二百匹御供米二俵野々山丹後守金三百匹御供米二俵高家宮原弾正金二千匹御供米二俵横瀬美濃守右は其重もなる大略に過ぎすと雖も上は將軍家より下庶民に及ふまて其の尊敬の篤かりしを知るに足るへし 社地の如きも彥根藩の領といへ自然一區域をなして恰も除地を以て過せらる されと維新以降地券發行山岳丈量の際誤つて境内と官林との區域を失ひ未た訂正を乞ふに到らずと雖も古史圖に徴して明なり
建物本社間口一尺七寸奥行二尺に寸石造 拜殿間口一丈四尺奥行九尺コケラ葺 境内地六坪一合五夕 群山重畳の中突兀として高く聳ゆるものは根本山なり 本社は即ち其項に鎭座す 滿山老樹欝茂奇巖峨々として飛泉珠を飛ばし異艸香を放つ 幽邃極まりて却つて寂寥眞に仙襄靈域たるの想あり 若し夫れ秋氣淸涼の候には楓樹千万錦を織り紅を染む美觀言ふべからず 一度び吟笻を曳いて登山せば淸風自ら湧くが如く靈氣身を襲ひて轉た天地の大寂に入るを感ぜん
役行者が富士山から東北を見ると瑞雲たなびく山が見えたのでやってきたのが飛駒の地,雲の根方に奇峰を見つけ根本山と名付けた。ここに天正元年1573良西が創立。桐生口と飛駒口にそれぞれ里宮の遥拝所がある。飛駒口は根古屋森林公園に,桐生口は田沼から群馬県に編入された今倉にあったらしいが,桐生川ダムに沈んだか。
例祭:5月3日登拝祭 11月15日
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-35丁
同村字根本山鎭座 無格社 根本山神社 祭神大山祇命 祭日四月二十四日十一月十五日 信徒五百十八戸總代六員 社掌藤倉若丸同村大字入彥間四二三番地住小野誠一郎同村大字上彥間二三一番地住 當社は天正元年1573四月一日先師良西行者の創立にして世襲の神地靈塲たり 舊記を按ずるに往昔役行者富士山に上ぼり東北を臨みしに瑞雲天に靆くの山あり即ち其雲を指して至れは雲の根方に古木蓊蔚として⾭苔滑かに荊棘途を埋めて怪岩地に峙つの奇峰あり故に之を根本山と名づく 後ち弘法大師東國飛錫の時登山して之れ神靈擁護の地なり後世遠近の輩群參の靈塲となるべしと云へり 果せる哉幾星霜を經て中興の法印良西桐生川の流れにしたかひ登山して相承の秘法を修し嫡々相傳ふる 二百餘年始めは信徒等參詣せんとせしに山中霹靂鳴動して咫尺を辮ぜざるか故に登山すること能はざりしが苦練修行の効空しからず遂に是の靈境を開らき信心の輩無羨に登參するを得るに到りしなりと かヽる由緒あれはにや舊領主井伊掃部頭は本社を祈願所と崇め毎歳祈禱を執行して神札を/長さ三尺檜神札/拜受するの例あり 又た高家宮原弾正大弼旗本野々山丹後守横瀬美濃守等も同じく神札を拜受して金穀物品を寄進すること其例となれり 且つ天保二年四月徳川家康公の妾歌浦殿病氣の際も當社永良印師御召を蒙むりて本丸に登城し病氣平愈の所禱をなしたる効により紫縮緬幕を寄進されたり 今ま神札に對する毎年の寄進高を列記すれば左の如くなりき 金千匹御供米二俵領主井伊侯より金二百匹御供米二俵野々山丹後守金三百匹御供米二俵高家宮原弾正金二千匹御供米二俵横瀬美濃守右は其重もなる大略に過ぎすと雖も上は將軍家より下庶民に及ふまて其の尊敬の篤かりしを知るに足るへし 社地の如きも彥根藩の領といへ自然一區域をなして恰も除地を以て過せらる されと維新以降地券發行山岳丈量の際誤つて境内と官林との區域を失ひ未た訂正を乞ふに到らずと雖も古史圖に徴して明なり
建物本社間口一尺七寸奥行二尺に寸石造 拜殿間口一丈四尺奥行九尺コケラ葺 境内地六坪一合五夕 群山重畳の中突兀として高く聳ゆるものは根本山なり 本社は即ち其項に鎭座す 滿山老樹欝茂奇巖峨々として飛泉珠を飛ばし異艸香を放つ 幽邃極まりて却つて寂寥眞に仙襄靈域たるの想あり 若し夫れ秋氣淸涼の候には楓樹千万錦を織り紅を染む美觀言ふべからず 一度び吟笻を曳いて登山せば淸風自ら湧くが如く靈氣身を襲ひて轉た天地の大寂に入るを感ぜん
八幡宮
[はちまんぐう]
栃木県佐野市・飛駒町6914→群馬県へ桐生市梅田町4-6914-1

主祭神:田原又太郎忠綱公霊 境内社:天神様(菅原大神,八幡大神,春日大神)
建久五年1194創建。田原又太郎忠綱終焉の地。
例祭:4月15日
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-36丁
同村字皆澤鎭座 無格社 八幡神社 祭神田原又太郎忠綱公靈 祭日陰曆三月十五日九月一日 信徒七十二戸總代三員 社掌藤倉若丸同村大字入彥間四二三番地住
今を去ること七百八年前即ち建久五年1194三月十五日の創立に係る是より先き治承四年高倉宮謀叛の暴あるや田原又太郎忠綱といへる人あり位は従四位上にして官は足利下野守たり力量衆に抽んて勇武絶倫を以て稱せられ殊に音聲は雷の如く一里の外に逹するといふされば是時も宇治川の戰に先陣となつて功あり平淸盛之を賞するに蝶の紋章を許るし且つ舊地足利に於て十二萬石を領すべきを以てす後建久五年に迨び故ありて今の飛駒の地に戰死すと傳ふ 其状況の口碑に残れる大略を擧ぐれば是時忠綱公には味方の手のもの散々に打なされ今は早や賴み少なく見へけれど英氣は日頃に百倍して單騎敵軍に突撃し當るを幸ひ薙立て切立て或は馬の蹄に掛け恰も夜叉の荒れたる如き振舞に縦横無盡と馳せ回はり爰を先途と戰へと甚は鐵石に非れば衆寡の勢當り難く今は是迄なりと飽まで血汐に塗みれたる刄を打振り一方の血路を開いて奔り出てある民家に潜伏せしに又もや烈しく追ひ來る敵のために見出され詮方盡きて再び戰を挑みしものから數か所の創痍に且つ戰ひ且つ退き次第々々に山の麓へ逹せしかば爰ぞと一聲をつと喚めいて項きへ馳せ上り或る大木の下に隠れ血を舐り息を凝らしていたりける开は今の神祠のある處即ち是なり 姑くして敵軍の率ひる一頭の白犬あり公の跡を躡ふて來たり 遂に其所在を見出したりけん狺々と吠へて之を敵に通知せしむ 時に敵将某遥に之を視て山鳥の羽すげたる征矢を番ヘて公を射る忠綱終に死す敵其死骸を棄て去る土民之を現今の世地に埋罪し其靈を祀り入彥間郷の鎭守と崇む是れ其の由緒の梗概なり 因にいふ爾來入彥間郷内にては白犬を飼ひ山鳥の羽毛を携ふることを忌むの傳へありて偶々兒童等の之を弄ふことあるも忽ち災凶到れりと今に及ぶまて相傳へて此事を警禁せり
建物本社間口五尺五寸奥行五尺五寸コケラ葺 拜殿間口二間奥行三間板葺
境内地八百七坪土地高燥にして古松老杉蔚然天外に聳立し殿
賑蒼然として晝尚を暗く古稚荘嚴の仙境なり飛駒川其下を回り屈曲透進として長蛇の奔る如く水急にして淸冽なり殊に此地岩石に富み劍崖千例或は途を要し或は川に峙ち龍婚虎据の状をなす其北浦より眺望するもの尤も絶佳たり嗚呼此濠趣心なき行旅と雖も件立低個去るに忍びさらん慎
に天然の圏謡といわんか有聲の詩といはんか筆描く能はず口語る能はず
建久五年1194創建。田原又太郎忠綱終焉の地。
例祭:4月15日
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-36丁
同村字皆澤鎭座 無格社 八幡神社 祭神田原又太郎忠綱公靈 祭日陰曆三月十五日九月一日 信徒七十二戸總代三員 社掌藤倉若丸同村大字入彥間四二三番地住
今を去ること七百八年前即ち建久五年1194三月十五日の創立に係る是より先き治承四年高倉宮謀叛の暴あるや田原又太郎忠綱といへる人あり位は従四位上にして官は足利下野守たり力量衆に抽んて勇武絶倫を以て稱せられ殊に音聲は雷の如く一里の外に逹するといふされば是時も宇治川の戰に先陣となつて功あり平淸盛之を賞するに蝶の紋章を許るし且つ舊地足利に於て十二萬石を領すべきを以てす後建久五年に迨び故ありて今の飛駒の地に戰死すと傳ふ 其状況の口碑に残れる大略を擧ぐれば是時忠綱公には味方の手のもの散々に打なされ今は早や賴み少なく見へけれど英氣は日頃に百倍して單騎敵軍に突撃し當るを幸ひ薙立て切立て或は馬の蹄に掛け恰も夜叉の荒れたる如き振舞に縦横無盡と馳せ回はり爰を先途と戰へと甚は鐵石に非れば衆寡の勢當り難く今は是迄なりと飽まで血汐に塗みれたる刄を打振り一方の血路を開いて奔り出てある民家に潜伏せしに又もや烈しく追ひ來る敵のために見出され詮方盡きて再び戰を挑みしものから數か所の創痍に且つ戰ひ且つ退き次第々々に山の麓へ逹せしかば爰ぞと一聲をつと喚めいて項きへ馳せ上り或る大木の下に隠れ血を舐り息を凝らしていたりける开は今の神祠のある處即ち是なり 姑くして敵軍の率ひる一頭の白犬あり公の跡を躡ふて來たり 遂に其所在を見出したりけん狺々と吠へて之を敵に通知せしむ 時に敵将某遥に之を視て山鳥の羽すげたる征矢を番ヘて公を射る忠綱終に死す敵其死骸を棄て去る土民之を現今の世地に埋罪し其靈を祀り入彥間郷の鎭守と崇む是れ其の由緒の梗概なり 因にいふ爾來入彥間郷内にては白犬を飼ひ山鳥の羽毛を携ふることを忌むの傳へありて偶々兒童等の之を弄ふことあるも忽ち災凶到れりと今に及ぶまて相傳へて此事を警禁せり
建物本社間口五尺五寸奥行五尺五寸コケラ葺 拜殿間口二間奥行三間板葺
境内地八百七坪土地高燥にして古松老杉蔚然天外に聳立し殿
賑蒼然として晝尚を暗く古稚荘嚴の仙境なり飛駒川其下を回り屈曲透進として長蛇の奔る如く水急にして淸冽なり殊に此地岩石に富み劍崖千例或は途を要し或は川に峙ち龍婚虎据の状をなす其北浦より眺望するもの尤も絶佳たり嗚呼此濠趣心なき行旅と雖も件立低個去るに忍びさらん慎
に天然の圏謡といわんか有聲の詩といはんか筆描く能はず口語る能はず
主祭神:味耜高彦根命 境内社:八坂神社
創建年月石燈籠不詳。鍋沢の吉田某が仙台の塩竈神社より勧請と伝わる。
安産祈願の社。
例祭:3月10日に近い日曜日 獅子舞奉納
創建年月石燈籠不詳。鍋沢の吉田某が仙台の塩竈神社より勧請と伝わる。
安産祈願の社。
例祭:3月10日に近い日曜日 獅子舞奉納
主祭神:天照皇大神 配神:譽田別命・迦具土命・伊耶那美命・大山祇命・宇賀之御魂命・日光山神 境内社:八坂神社・疱瘡神社(道祖比売神) 境外社:八坂神社・山神社(大山祇神)
以前は町屋395に鎭座した。かつては八坂神社大祭には神輿が六か村を回り,花屋台が出て盛大だったが,いまは神明宮拝殿に納めてある神輿を出して飾るだけとなった。
例祭:3月15日 境外社八坂神社大祭:7月21日
以前は町屋395に鎭座した。かつては八坂神社大祭には神輿が六か村を回り,花屋台が出て盛大だったが,いまは神明宮拝殿に納めてある神輿を出して飾るだけとなった。
例祭:3月15日 境外社八坂神社大祭:7月21日
主祭神:菅原道真公 境内社:浅間神社・稲荷神社(豊受姫命)
詳細不詳。
例祭:2月25日 9月16日
詳細不詳。
例祭:2月25日 9月16日
主祭神:天児屋根命 境内社:大杉神社 境外社:雷電神社
飛駒町1486の駒形神社より前に神山家の祖が創建しい信仰していた。神山家が宮原に子孫を居住させたときに駒形神社を祀るので,駒形神社の本宮と伝わる。
例祭:4月10日に近い日曜日
飛駒町1486の駒形神社より前に神山家の祖が創建しい信仰していた。神山家が宮原に子孫を居住させたときに駒形神社を祀るので,駒形神社の本宮と伝わる。
例祭:4月10日に近い日曜日
主祭神:大山祇命
詳細不詳。
例祭:4月1日 9月16日
詳細不詳。
例祭:4月1日 9月16日
主祭神:倉稲魂命 境内社:秋葉神社(火産霊命)・山神社・稲荷神社(豊受姫命)
詳しいことは分からない。
例祭:3月28日
詳しいことは分からない。
例祭:3月28日
主祭神:伊弉冊命・速玉之男命・事解之男命 境内社:琴平神社ほか5社
齊明天皇七年661というとんでもない創建説が伝わる。『下野神社沿革誌』には文久二年1862の火災の際,左甚五郎作の木製狛犬が動き出した逸話が載っている。
御神木の榧kayaは目通り5m超,樹高20m,樹齢500年超。
例祭:4月10日
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-38丁
三好村大字船越鎭座 村社 熊野神社 祭神 祭日三月十五日九月十五日 氏子六十二戸 社掌阿部覚人同村同大字五十一番地住
社傳に曰く本社は齊明七年661三月十五日紀州熊野本宮より當佐野上へ鎭座したるものにして其後天長元年824中上毛野に赤岩左近といへるもの者*ありて武藏國羽生あたりの強盗と共に常に黨類を催して人民を脅し財物を掠め暴害盆す甚しく衆其堵に安んする能はす而して強賊等は上武の間を横行して變出鬼没極りなく勢日に猖獗なり 時に前従二位中納言贈正一位大政大臣長良卿大に之を憂へ神力に依りて効を奏せんと欲し遂に本社に祈誓をかけて賊を討伐せしめ給ふ然るにさしもの豪賊風の木の葉を捲くか如く忽ち蔟滅しけれは只管大神の靈驗に感じ一族弾正聖大弼良綱に仰あつて禮代のため此に宮閣を再建せしめけるよしは慥かに記録に明かなり 文久二年1862三月の出火にて本社拜殿雜舎共に類焼に罹りしか幣殿本社は元治元年1864を以て再建し拜殿は明治廿七年に到り氏子諸氏の盡力によって再建するを得たり 又た弘化二年十月地頭中山大助より武運長久の祈禱免として神主阿部家所有地の内上田一反九畝二十二歩新田三畝十五歩山ニヶ所六反一畝歩を本社除地に寄附せられたり
(以下細字)/此社につきいと珍らしき話柄あれは掲くへし頃は文久二年1862三月十八日折しも西風烈しく樹枝を折り砂を飛ばす程なりしか何れよのか火は熾んに燃へ來りて神主阿部家は勿論本社拜殿にまてみるみる燃へうつりたり風急なれば人々防くに術なくあれよあれよと眺むるのみ時に阿部氏は不在にて夫人ツヤ子のみ必死となりて奴僕を指揮し器具財物等を運び出さんと猛火の傍りを往來せる時何地より來りけん一匹の唐犬常にツヤ子に随ひて奔走し其傍を離れす其時は危危の塲合とて心にもとめさりしか程すぎて鎭火の後考へみるに飛騨の甚五郎が作なる木狗は嘗てより本社に納めありしが定めて名人の細工とて魂のこもり居ることゆへ神の惜しませたまいしにやと思いつき阿部氏歸宅の後此ことをはなせりにさもありなんとて氏もいたく其災に罹りたるを惜みしと云ふ/
建物 本社間口六尺三寸奥行五尺一寸瓦葺 拜殿間口九尺奥行五尺七寸瓦葺 幣殿九尺間口奥行二間瓦葺 神樂殿間口二間奥行三間半 鳥居一基 石燈籠二基 境内地四百坪
本社は未に向ひて大字の中央小高き地處にあり 坤より西方には人家を臨み東北には田畝を控へたり 境内には⾭苔滑らに殆んと三百年を繼たらんと覺しき木あまたありされど重に繁茂せるは杉にして之も百有餘年前後のものと思はる 淸涼の氣を吸はんと欲するもの賛稱して措ざる勝地なり
齊明天皇七年661というとんでもない創建説が伝わる。『下野神社沿革誌』には文久二年1862の火災の際,左甚五郎作の木製狛犬が動き出した逸話が載っている。
御神木の榧kayaは目通り5m超,樹高20m,樹齢500年超。
例祭:4月10日
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-38丁
三好村大字船越鎭座 村社 熊野神社 祭神 祭日三月十五日九月十五日 氏子六十二戸 社掌阿部覚人同村同大字五十一番地住
社傳に曰く本社は齊明七年661三月十五日紀州熊野本宮より當佐野上へ鎭座したるものにして其後天長元年824中上毛野に赤岩左近といへるもの者*ありて武藏國羽生あたりの強盗と共に常に黨類を催して人民を脅し財物を掠め暴害盆す甚しく衆其堵に安んする能はす而して強賊等は上武の間を横行して變出鬼没極りなく勢日に猖獗なり 時に前従二位中納言贈正一位大政大臣長良卿大に之を憂へ神力に依りて効を奏せんと欲し遂に本社に祈誓をかけて賊を討伐せしめ給ふ然るにさしもの豪賊風の木の葉を捲くか如く忽ち蔟滅しけれは只管大神の靈驗に感じ一族弾正聖大弼良綱に仰あつて禮代のため此に宮閣を再建せしめけるよしは慥かに記録に明かなり 文久二年1862三月の出火にて本社拜殿雜舎共に類焼に罹りしか幣殿本社は元治元年1864を以て再建し拜殿は明治廿七年に到り氏子諸氏の盡力によって再建するを得たり 又た弘化二年十月地頭中山大助より武運長久の祈禱免として神主阿部家所有地の内上田一反九畝二十二歩新田三畝十五歩山ニヶ所六反一畝歩を本社除地に寄附せられたり
(以下細字)/此社につきいと珍らしき話柄あれは掲くへし頃は文久二年1862三月十八日折しも西風烈しく樹枝を折り砂を飛ばす程なりしか何れよのか火は熾んに燃へ來りて神主阿部家は勿論本社拜殿にまてみるみる燃へうつりたり風急なれば人々防くに術なくあれよあれよと眺むるのみ時に阿部氏は不在にて夫人ツヤ子のみ必死となりて奴僕を指揮し器具財物等を運び出さんと猛火の傍りを往來せる時何地より來りけん一匹の唐犬常にツヤ子に随ひて奔走し其傍を離れす其時は危危の塲合とて心にもとめさりしか程すぎて鎭火の後考へみるに飛騨の甚五郎が作なる木狗は嘗てより本社に納めありしが定めて名人の細工とて魂のこもり居ることゆへ神の惜しませたまいしにやと思いつき阿部氏歸宅の後此ことをはなせりにさもありなんとて氏もいたく其災に罹りたるを惜みしと云ふ/
建物 本社間口六尺三寸奥行五尺一寸瓦葺 拜殿間口九尺奥行五尺七寸瓦葺 幣殿九尺間口奥行二間瓦葺 神樂殿間口二間奥行三間半 鳥居一基 石燈籠二基 境内地四百坪
本社は未に向ひて大字の中央小高き地處にあり 坤より西方には人家を臨み東北には田畝を控へたり 境内には⾭苔滑らに殆んと三百年を繼たらんと覺しき木あまたありされど重に繁茂せるは杉にして之も百有餘年前後のものと思はる 淸涼の氣を吸はんと欲するもの賛稱して措ざる勝地なり
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
主祭神:天津兒屋根命 配神:大己貴命・大日孁貴命・軻遇突智命・大山祇命・菅原道真公・瀬織津姫命・水速玉命・水速貴命・大雷神命・火産霊命・白山姫命 境内社:稲荷神社・天満宮
天慶五年942藤原秀郷が創建。本殿に彩色彫刻。
例祭:11月23日
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
安蘇郡 三騎大明神 上船越 神宮寺
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-38-39丁
三好村大字船越三騎山鎭座 村社 三騎神社 祭神天兒屋根命 建物本社間口五尺奥行四尺 幣殿間口一間奥行一間四尺 拜殿間口二間四尺奥行一間四尺 末社二社 氏子百十一戸
本社創立は天慶五年942九月十五日にして藤原秀郷の勸請なり 后天正十八年1590船越六郎再建せしも正保三年燹火の災に罹り后享保十年1725中氏子村民造營す 社域百四十二坪を有す
天慶五年942藤原秀郷が創建。本殿に彩色彫刻。
例祭:11月23日
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
安蘇郡 三騎大明神 上船越 神宮寺
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-38-39丁
三好村大字船越三騎山鎭座 村社 三騎神社 祭神天兒屋根命 建物本社間口五尺奥行四尺 幣殿間口一間奥行一間四尺 拜殿間口二間四尺奥行一間四尺 末社二社 氏子百十一戸
本社創立は天慶五年942九月十五日にして藤原秀郷の勸請なり 后天正十八年1590船越六郎再建せしも正保三年燹火の災に罹り后享保十年1725中氏子村民造營す 社域百四十二坪を有す
主祭神:橘豊日命・豊聡耳命(聖徳太子) 境内社:雷電神社・二荒山神社・三日月神社・白山神社・八坂神社・白山神社
天慶四年941藤原秀郷が創建。貞享年間1684~88焼失。元禄六年1693再建。明治四十三年1910焼失。大正六年1917再建なって正遷座式。
例祭:4月10日
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
安蘇郡 吉大明神 下船越 蓮乗院
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-39丁
三好村大字船越字上の宮鎭座 村社 上宮神社 祭神橘豊日命 豊聰耳命 建物本社一宇 拜殿間口三間半奥行三間半 水盥屋間口一間奥行四尺
本社創建は天慶四年941二月廿二日にして藤原秀郷の勸請なり 后佐野家にて再建 其后貞享年中祝融の災により灰儘に歸す 元録六年二月村民の再建する所にして社域七百廿五坪を有す
天慶四年941藤原秀郷が創建。貞享年間1684~88焼失。元禄六年1693再建。明治四十三年1910焼失。大正六年1917再建なって正遷座式。
例祭:4月10日
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
安蘇郡 吉大明神 下船越 蓮乗院
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-39丁
三好村大字船越字上の宮鎭座 村社 上宮神社 祭神橘豊日命 豊聰耳命 建物本社一宇 拜殿間口三間半奥行三間半 水盥屋間口一間奥行四尺
本社創建は天慶四年941二月廿二日にして藤原秀郷の勸請なり 后佐野家にて再建 其后貞享年中祝融の災により灰儘に歸す 元録六年二月村民の再建する所にして社域七百廿五坪を有す
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
主祭神:鵜葺屋葺不合命・天児屋根命・戸矢子[へやこ]七郎有綱朝臣命
『下野神社沿革誌』は「にして」が2回出てきて分かりにくいが,戸矢子七郎有綱が鞍掛山に落ち延びて自害する。藤原秀郷の末裔なので村人が祠を建てて祀り鞍掛大明神と称した。三度の修造のうち元禄は年号が定かでない。元禄元年1688(『栃木県神社誌』平成18年版)または元禄十年1697(『下野神社沿革誌』)修繕。『栃木県神社誌』は元禄元年でなく一年と記載しているので十の違いかもしれない。『下野神社沿革誌』は十年再建。
本殿には鮮やかな着色彫刻が施されている。
正徳五年1715石燈籠。
例祭:4月第二日曜日
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
安蘇郡 正一位 鞍掛大明神 戸室 亀田淡路
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-39丁
三好村大字戸室字宮前鎭座 村社 鞍掛神社 祭神藤原有網靈命 建物本社間口一間奥行一間 拜殿間口三間奥行二間 末社六社 氏子百二十四戸
本社創立は文治二年1186十一月にして鎭守府將軍田原藤太秀郷十五代孫中宮亮戸矢子七郎有綱にして故ありて爰に祭祀す 后寛永十三年1636七月及ひ元録十年二月延享二年1745十月の再建なり 社域百五十坪民有第二種にあり
『下野神社沿革誌』は「にして」が2回出てきて分かりにくいが,戸矢子七郎有綱が鞍掛山に落ち延びて自害する。藤原秀郷の末裔なので村人が祠を建てて祀り鞍掛大明神と称した。三度の修造のうち元禄は年号が定かでない。元禄元年1688(『栃木県神社誌』平成18年版)または元禄十年1697(『下野神社沿革誌』)修繕。『栃木県神社誌』は元禄元年でなく一年と記載しているので十の違いかもしれない。『下野神社沿革誌』は十年再建。
本殿には鮮やかな着色彫刻が施されている。
正徳五年1715石燈籠。
例祭:4月第二日曜日
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
安蘇郡 正一位 鞍掛大明神 戸室 亀田淡路
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-39丁
三好村大字戸室字宮前鎭座 村社 鞍掛神社 祭神藤原有網靈命 建物本社間口一間奥行一間 拜殿間口三間奥行二間 末社六社 氏子百二十四戸
本社創立は文治二年1186十一月にして鎭守府將軍田原藤太秀郷十五代孫中宮亮戸矢子七郎有綱にして故ありて爰に祭祀す 后寛永十三年1636七月及ひ元録十年二月延享二年1745十月の再建なり 社域百五十坪民有第二種にあり
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
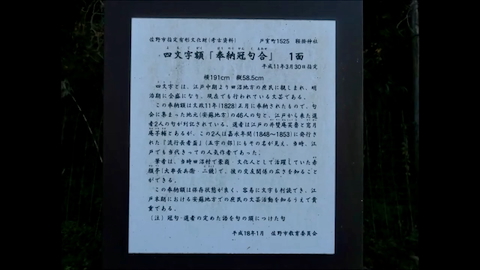 |
主祭神:譽田別命 境内社:天神宮・熊野・稲荷・諏訪神社ほか5社
『下野神社沿革誌』は「宮崎」で記録したが「岩崎」の誤記または誤植だろう。岩崎は三好村で一致,昭和三十九年1964の岩崎の八幡宮の記録の本社,拝殿の間口奥行も一致。氏子戸数もほぼ一致。
御神体の応神天皇像は木曽家に伝来し,木曾佐馬介義持が岩崎弥太夫と変名し岩崎家が氏神として奉祭したが明応八年1499から村の神社とした。
明治四十二年1909稲荷神社,八坂神社を合祀。
本殿の素盞嗚命の八岐大蛇退治などの彩色彫刻がみごと。
例祭:4月10日
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
安蘇郡 八幡宮 岩崎 西光院
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-39丁
三好村大字宮崎鎭座 本社 八幡宮 祭神譽田別命 建物本社間口一間奥行一間 拜殿間口三間奥行二間 石燈籠一基 末社二社 氏子百四十九戸 社掌阿部覚人同村大字船越住
本社創立年月不詳 社域百四十八坪宇三角に在り
『下野神社沿革誌』は「宮崎」で記録したが「岩崎」の誤記または誤植だろう。岩崎は三好村で一致,昭和三十九年1964の岩崎の八幡宮の記録の本社,拝殿の間口奥行も一致。氏子戸数もほぼ一致。
御神体の応神天皇像は木曽家に伝来し,木曾佐馬介義持が岩崎弥太夫と変名し岩崎家が氏神として奉祭したが明応八年1499から村の神社とした。
明治四十二年1909稲荷神社,八坂神社を合祀。
本殿の素盞嗚命の八岐大蛇退治などの彩色彫刻がみごと。
例祭:4月10日
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
安蘇郡 八幡宮 岩崎 西光院
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-39丁
三好村大字宮崎鎭座 本社 八幡宮 祭神譽田別命 建物本社間口一間奥行一間 拜殿間口三間奥行二間 石燈籠一基 末社二社 氏子百四十九戸 社掌阿部覚人同村大字船越住
本社創立年月不詳 社域百四十八坪宇三角に在り
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
主祭神:武甕槌命
玉垣のある立派な神社。八幡宮の西。
玉垣のある立派な神社。八幡宮の西。
▊飛駒村
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902五月十日發行 巻ニ-34丁
本村は地域現時の新合村と接し上彥間下彥間とは素より離る可からさる種々の關係なきに非らす雖も上下彥間を一の自治村となすは地域に於て廣大に過くる感ありて本村は舊上彥間村一村を獨立せしめ以て一自治村をなせしものにして其幅員東西一里南北三里餘面積四千六百五十四町餘歩を有せり 地勢北より東に亘りて山脉重畳連亘し西一帶亦幾多の山脉起伏して足利郡との郡界をなせり 根本山は本村の東北端に十二岳は西北端に聳ひ高嶽を以て名あり 東は野上村に隣し南は新合村に接し全村土地自ら高峻にして中央より以南は南下するに従ひ低くして其間耕地開くるあるも全村の面積の十分の二位に過きす 村民は農耕を營むものあれと多くは木材薪炭業に従事す 土地凌角にして到底農業の利を得るに難きに依れり 其物產として木材薪炭の外近時養蠶製糸業の進歩し產額少なからす且紙及ひ石灰等を產せり
古來の沿革に就ては往時佐野氏の所領たり 尋て佐野信吉領地を没収せらるヽに際し幕府代官の支配となり後幾多の領主を經て寛永十年中彥根井伊家の領地となる 明治維新の際彥根藩の支配となり然して明治四年栃木縣の所轄となり町村制實施の際一村獨立して一自治村となり飛駒村と改稱す 本村には村社一社及ひ有名なる無格社根本山神社外一社ありて氏子戸數五百十餘戸人口三千二百三十餘人あり
▊三好村 *『下野神社沿革誌』明治三十五年1902五月十日發行 巻ニ-37丁
本村は船越,岩崎,戸室の舊三村を合併してー自治區となせしものなり 其位置北は野上村南は田沼町東は葛生町及ひ常磐村に西は新合村と境界相接せり 野上川は村の東方一帶を限りて流れ水利用水の便多く之に係れり 村民朴直にして勤倹の風あり専ら農業を勉め交際親密なり
古來の沿革に付ては往古佐野氏の所領にして其子孫連綿として相幾き之を領せり 后各地とも或は代官知行所となり其他各藩の領地となりしか明治維新の后栃木縣に屬し次て町村制實施に至り現今の一村とはなりぬ 本村には村社五社ありて其氏子戸數五百餘戸人口三千二百二十餘人あり
本村は地域現時の新合村と接し上彥間下彥間とは素より離る可からさる種々の關係なきに非らす雖も上下彥間を一の自治村となすは地域に於て廣大に過くる感ありて本村は舊上彥間村一村を獨立せしめ以て一自治村をなせしものにして其幅員東西一里南北三里餘面積四千六百五十四町餘歩を有せり 地勢北より東に亘りて山脉重畳連亘し西一帶亦幾多の山脉起伏して足利郡との郡界をなせり 根本山は本村の東北端に十二岳は西北端に聳ひ高嶽を以て名あり 東は野上村に隣し南は新合村に接し全村土地自ら高峻にして中央より以南は南下するに従ひ低くして其間耕地開くるあるも全村の面積の十分の二位に過きす 村民は農耕を營むものあれと多くは木材薪炭業に従事す 土地凌角にして到底農業の利を得るに難きに依れり 其物產として木材薪炭の外近時養蠶製糸業の進歩し產額少なからす且紙及ひ石灰等を產せり
古來の沿革に就ては往時佐野氏の所領たり 尋て佐野信吉領地を没収せらるヽに際し幕府代官の支配となり後幾多の領主を經て寛永十年中彥根井伊家の領地となる 明治維新の際彥根藩の支配となり然して明治四年栃木縣の所轄となり町村制實施の際一村獨立して一自治村となり飛駒村と改稱す 本村には村社一社及ひ有名なる無格社根本山神社外一社ありて氏子戸數五百十餘戸人口三千二百三十餘人あり
▊三好村 *『下野神社沿革誌』明治三十五年1902五月十日發行 巻ニ-37丁
本村は船越,岩崎,戸室の舊三村を合併してー自治區となせしものなり 其位置北は野上村南は田沼町東は葛生町及ひ常磐村に西は新合村と境界相接せり 野上川は村の東方一帶を限りて流れ水利用水の便多く之に係れり 村民朴直にして勤倹の風あり専ら農業を勉め交際親密なり
古來の沿革に付ては往古佐野氏の所領にして其子孫連綿として相幾き之を領せり 后各地とも或は代官知行所となり其他各藩の領地となりしか明治維新の后栃木縣に屬し次て町村制實施に至り現今の一村とはなりぬ 本村には村社五社ありて其氏子戸數五百餘戸人口三千二百二十餘人あり




