八坂神社
[やさか神社]
栃木県佐野市・葛生西1-10-36

主祭神:素盞嗚命 配神:稲田姫命・大名持命 境内社:手摩乳大神・足摩乳大神・応神天皇の八幡宮・疱瘡大神・三日月大神・稲荷大神・市神・松尾大神・愛宕大神・龍神・熊野大神・三峯大神・北野大神・浅間大神
建仁元年1201に牧村の天王澤に牛頭天王を祀ったことに始る。
暦応(北朝)二年1339の大洪水で社殿流失。下流の葛ケ原山本の里に流れ着いた神饌と神鏡を拾った石川氏が葛生2703番地,現在の葛生西1丁目の現社地に祠を建てて祀った。明治十年1877郷社。
昭和三年1928拝殿新築,昭和十年1935神樂殿など造営。
例祭:7月第三土曜日
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
安蘇郡 牛頭天王宮 葛生 柴田安芸
*『下野掌覧』万延元年1860 安蘇郡之部
天王神社 葛生町鎮座 祭主戸賀崎氏ナリ
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-20丁
葛生町大字葛生字倭町鎭座 郷社 八坂神社 祭神健須佐之雄命 祭日陰曆六月十三日九月十三日 氏子百八十戸總代三員 社司毛利眞守仝郡田沼町大字多田住 社掌富田彌四郎仝町大字仝七六番地住
社傳に曰く土御門天皇の御宇建仁元年1201の春に當り本郡到る處疫癘の流行劇しく勢益猖獗なるを以て其年六月同郡牧村の郷民は疫癘解除五穀成熟を禱るため新たに一社を勸請し牛頭天王と崇む 今の天王澤の地は即ち其故迹なり 初め比企藤七郎能宗といへる人神主職を奉じたりしが後に氏を宮田と改む 藤七郎能宗の子宮田外記能宣より累世相承けて其職を奉ぜり 神威赫灼衆民倚安四隣無事なりき 然るに降つて曆應二年1339に迨び洪水汎濫家屋を流出し人畜の死傷せるもの又算なし 時に神殿漂潰して神幣水に従つて流れ終に山本の里[今の葛生町を云ふ]に止り着く 石川某之を拾ひ上げ神慮の存する所を忖り衆民と共に現今の處に一社を創建して崇め祀る本社の由來は即ち是なり 後ち終に宮田氏随従し來り尚ほ神主職を奉ず寶永年間宮田を柴田と改め文政年間又た戸賀崎と改め明治の初年先祖能宣より十二代の裔壹岐正精敏に迨んて再び宮田に復す 當代彌四郎氏に到るまて三十三代の久しき統を更へずして本社に事つるは蓋だし神意の偶然ならざるものあるに似たり 明治五年神號を八坂神社と改稱し葛生町外九宿町村の郷社と定めらる 是より威靈彌よ驗著ならん
建物 本社間口二間奥行一間銅葺 拜殿間口三間奥行二間板葺 神庫一棟 石燈籠三基 石華表一基 末社十四社
境内地五百坪を有し倭町の西側にありて東向きに建てられたり 東南北三面は町家を控ひ西僅に沃野を望む 馬塲を入りて兩側にいと大なる玉椿二株あり 梅櫻又た枝を參へて春色の光景に乏しからず 境内には重に杉銀杏樫の大木の蓊鬱たるを見る中に一際すくれて目覺しきはいと古ひたる杉の樹の三股に枝をひろげて遠く雲表に屹立せるものにして恰も高士一たび怒つて髪天を衝くの慨あり 要するに未だ塵懐を脱せすと雖も長風蓬然淸嵐の颯々たるを聞かは無量の淸興萬斛の雅趣油然として湧き又た一勝區たるに妨げざるの地なり
建仁元年1201に牧村の天王澤に牛頭天王を祀ったことに始る。
暦応(北朝)二年1339の大洪水で社殿流失。下流の葛ケ原山本の里に流れ着いた神饌と神鏡を拾った石川氏が葛生2703番地,現在の葛生西1丁目の現社地に祠を建てて祀った。明治十年1877郷社。
昭和三年1928拝殿新築,昭和十年1935神樂殿など造営。
例祭:7月第三土曜日
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
安蘇郡 牛頭天王宮 葛生 柴田安芸
*『下野掌覧』万延元年1860 安蘇郡之部
天王神社 葛生町鎮座 祭主戸賀崎氏ナリ
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-20丁
葛生町大字葛生字倭町鎭座 郷社 八坂神社 祭神健須佐之雄命 祭日陰曆六月十三日九月十三日 氏子百八十戸總代三員 社司毛利眞守仝郡田沼町大字多田住 社掌富田彌四郎仝町大字仝七六番地住
社傳に曰く土御門天皇の御宇建仁元年1201の春に當り本郡到る處疫癘の流行劇しく勢益猖獗なるを以て其年六月同郡牧村の郷民は疫癘解除五穀成熟を禱るため新たに一社を勸請し牛頭天王と崇む 今の天王澤の地は即ち其故迹なり 初め比企藤七郎能宗といへる人神主職を奉じたりしが後に氏を宮田と改む 藤七郎能宗の子宮田外記能宣より累世相承けて其職を奉ぜり 神威赫灼衆民倚安四隣無事なりき 然るに降つて曆應二年1339に迨び洪水汎濫家屋を流出し人畜の死傷せるもの又算なし 時に神殿漂潰して神幣水に従つて流れ終に山本の里[今の葛生町を云ふ]に止り着く 石川某之を拾ひ上げ神慮の存する所を忖り衆民と共に現今の處に一社を創建して崇め祀る本社の由來は即ち是なり 後ち終に宮田氏随従し來り尚ほ神主職を奉ず寶永年間宮田を柴田と改め文政年間又た戸賀崎と改め明治の初年先祖能宣より十二代の裔壹岐正精敏に迨んて再び宮田に復す 當代彌四郎氏に到るまて三十三代の久しき統を更へずして本社に事つるは蓋だし神意の偶然ならざるものあるに似たり 明治五年神號を八坂神社と改稱し葛生町外九宿町村の郷社と定めらる 是より威靈彌よ驗著ならん
建物 本社間口二間奥行一間銅葺 拜殿間口三間奥行二間板葺 神庫一棟 石燈籠三基 石華表一基 末社十四社
境内地五百坪を有し倭町の西側にありて東向きに建てられたり 東南北三面は町家を控ひ西僅に沃野を望む 馬塲を入りて兩側にいと大なる玉椿二株あり 梅櫻又た枝を參へて春色の光景に乏しからず 境内には重に杉銀杏樫の大木の蓊鬱たるを見る中に一際すくれて目覺しきはいと古ひたる杉の樹の三股に枝をひろげて遠く雲表に屹立せるものにして恰も高士一たび怒つて髪天を衝くの慨あり 要するに未だ塵懐を脱せすと雖も長風蓬然淸嵐の颯々たるを聞かは無量の淸興萬斛の雅趣油然として湧き又た一勝區たるに妨げざるの地なり
 |
 |
 |
 |
 |
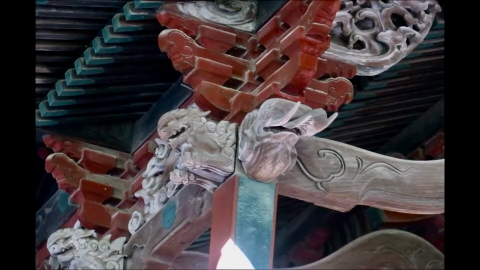 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 牛頭天王 |
主祭神:武甕槌命 境内社:八坂神社・八幡神社・木市大神・菅原大神
延暦八年789創建の古社。治承元年1177大洪水で流失,400mほど流された先の岩窟から大蛇が抜け出て泳いだと伝わる。明治元年1868葛生の中心部泉町の西に遷宮。明治八年1875幣殿・拝殿新築。明治十七年1884花崗岩鳥居奉納。昭和四十六年1971本殿改築。
例祭:11月15日
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
安蘇郡 鹿島大明神 葛生 村樫摂津
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-21丁
葛生町大字葛生字泉町鎭座 村社 鹿島神社 祭神武甕槌命 祭日陽曆五月一日陰曆十一月十五日 氏子四百四十八戸總代五員 社掌村樫榮次仝町大字仝二百五番地住
社傳に曰く桓武天皇の御宇延曆八年789四月朔日坂上田村麿奥夷征伐の際天下太平祈願のため山本里[當時葛生]の北山奥に建立し鹿島太神と稱したるより創り靈現殊に著しきを以て後に葛生以北梅澤以北山中の十八ヶ村崇祀の鎭守となり星霜を經る三百九十九*[388?]年治承元年1177の夏に當り霖雨の末疾風雷鳴劇しく起り石を飛はし枝を折り其勢ひ凄なんと云ふばかりなし天地爲めに震ひ河海爲めに溢れ山崩れ谷嘯き家屋の破損人畜の死傷枚擧するに遑あらず實に空前絶後の大洪水なりき是時鹿島の神殿も此れがために流出し凡そ四丁程隔りたる處に止まりしに忽ち大蛇傍への岩窟より抜け出しと云ふこと口碑に残り今も其神殿の流れとまりし處を宮澤と稱し且つ大蛇の抜穴をも存せり 今も尚ほ山脈の崩壊せる土中よりは往々朽木,埋木などを發見せるよしなり 舊社殿に通ずる大門の迹僅かに存す 其長さ四百餘間あり 又た鳥居の處に老杉二株あり注連曳杉と云ふ 开は毎歳祭禮の時注連を是の杉に張りて祭るの例あるによりて此の名ありとか 文治年85~90右大將賴朝覇府を鎌倉に建し比ひ十八ヶ村の氏子祭禮の式に於ける座次を論じたる末終に分れて神靈を各地に分祀することヽなり是に随つて神官も又た各地に置れたりといふ され共就中當社のみは衆庶の信仰衰へず依然敬崇のもの日に其多きを加へ其威徳卒いて各村にまても及ほせり 弘長年間南家藤原右大稱良定二十一代の裔次郎太夫吉政なるもの此地に來り一村落を開らき自ら神主となる 地多く樫を植ゆ故に村樫を以て氏となす 其子四人あり各地に散じて同じく神主となり氏を各別ち改めて持田村樫矢部林の四氏となる 大祖吉政より明治年間榮次に至るまて二十八代代々本社に奉祀す 當社は中古佐野家の崇敬する處となり高六十三石の神領を奉ぜられ徳川政府の頃は常に時の領主に欽仰せらる 明治五年の改正に際し氏子一同相謀り葛生町の中央字泉町の西に新たに社殿を營み鹿島神社と改稱して村社に定めらる
建物 本社間口六尺二寸奥行六尺 拜殿間口四間奥行二間半 末社六社
境内地ー反十九歩本社位置は泉町の西側にあり社は南向きにして南北町家を控ヘ西には洋々たる田甫を望む 茅軒其間に點々たり 境内には疎林空闊幽邃淸雅塵懐自ら洗ふか如とし
延暦八年789創建の古社。治承元年1177大洪水で流失,400mほど流された先の岩窟から大蛇が抜け出て泳いだと伝わる。明治元年1868葛生の中心部泉町の西に遷宮。明治八年1875幣殿・拝殿新築。明治十七年1884花崗岩鳥居奉納。昭和四十六年1971本殿改築。
例祭:11月15日
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
安蘇郡 鹿島大明神 葛生 村樫摂津
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-21丁
葛生町大字葛生字泉町鎭座 村社 鹿島神社 祭神武甕槌命 祭日陽曆五月一日陰曆十一月十五日 氏子四百四十八戸總代五員 社掌村樫榮次仝町大字仝二百五番地住
社傳に曰く桓武天皇の御宇延曆八年789四月朔日坂上田村麿奥夷征伐の際天下太平祈願のため山本里[當時葛生]の北山奥に建立し鹿島太神と稱したるより創り靈現殊に著しきを以て後に葛生以北梅澤以北山中の十八ヶ村崇祀の鎭守となり星霜を經る三百九十九*[388?]年治承元年1177の夏に當り霖雨の末疾風雷鳴劇しく起り石を飛はし枝を折り其勢ひ凄なんと云ふばかりなし天地爲めに震ひ河海爲めに溢れ山崩れ谷嘯き家屋の破損人畜の死傷枚擧するに遑あらず實に空前絶後の大洪水なりき是時鹿島の神殿も此れがために流出し凡そ四丁程隔りたる處に止まりしに忽ち大蛇傍への岩窟より抜け出しと云ふこと口碑に残り今も其神殿の流れとまりし處を宮澤と稱し且つ大蛇の抜穴をも存せり 今も尚ほ山脈の崩壊せる土中よりは往々朽木,埋木などを發見せるよしなり 舊社殿に通ずる大門の迹僅かに存す 其長さ四百餘間あり 又た鳥居の處に老杉二株あり注連曳杉と云ふ 开は毎歳祭禮の時注連を是の杉に張りて祭るの例あるによりて此の名ありとか 文治年85~90右大將賴朝覇府を鎌倉に建し比ひ十八ヶ村の氏子祭禮の式に於ける座次を論じたる末終に分れて神靈を各地に分祀することヽなり是に随つて神官も又た各地に置れたりといふ され共就中當社のみは衆庶の信仰衰へず依然敬崇のもの日に其多きを加へ其威徳卒いて各村にまても及ほせり 弘長年間南家藤原右大稱良定二十一代の裔次郎太夫吉政なるもの此地に來り一村落を開らき自ら神主となる 地多く樫を植ゆ故に村樫を以て氏となす 其子四人あり各地に散じて同じく神主となり氏を各別ち改めて持田村樫矢部林の四氏となる 大祖吉政より明治年間榮次に至るまて二十八代代々本社に奉祀す 當社は中古佐野家の崇敬する處となり高六十三石の神領を奉ぜられ徳川政府の頃は常に時の領主に欽仰せらる 明治五年の改正に際し氏子一同相謀り葛生町の中央字泉町の西に新たに社殿を營み鹿島神社と改稱して村社に定めらる
建物 本社間口六尺二寸奥行六尺 拜殿間口四間奥行二間半 末社六社
境内地ー反十九歩本社位置は泉町の西側にあり社は南向きにして南北町家を控ヘ西には洋々たる田甫を望む 茅軒其間に點々たり 境内には疎林空闊幽邃淸雅塵懐自ら洗ふか如とし
山菅
安蘇澤神社
[あそざわ神社]
佐野市・山菅町3539
配神:[高龗神]

旧地名:安蘇郡田沼町大字山菅
主祭神:別雷神
配神:高龗神[たかおかみのかみ],大宮売命,水波乃女命
下野国の在庁長官であった藤原秀郷(根古谷唐澤城主田原藤太)が霊夢により武運長久,領土安穏祈願のため勧請。天明七年1787社殿を建築。山菅鎮守として尊崇されてきた。秀郷が勧請した多数の神社のひとつ。
安蘇澤鎭守にもかかわらず地図に載せてもらえないので探しにくいが,葛生原人発掘跡から見て,道路を挟んで南東方面向かい側の山に鎮座。
目印は正明寺と山菅公民館。この先の山野井採石工業の前。
大正十年十月の御影石明神鳥居。
「常夜燈 安政五午年九月吉日」1858
境内社として記録されている「八坂神社,浅間神社,菅原神社,秋葉神社」のどれか不明だが,拝殿右手の石垣に2社並んでいる。「x納xx三社xx xxxx丁卯」だけ読める石燈籠が2基。
-------------------
本殿:明神造銅版葺 拝殿:入母屋造亜鉛葺 幣殿:切妻造亜鉛葺
例祭:10月19
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
安蘇郡 雷天宮大富士権現 山菅 山菅氏
主祭神:別雷神
配神:高龗神[たかおかみのかみ],大宮売命,水波乃女命
下野国の在庁長官であった藤原秀郷(根古谷唐澤城主田原藤太)が霊夢により武運長久,領土安穏祈願のため勧請。天明七年1787社殿を建築。山菅鎮守として尊崇されてきた。秀郷が勧請した多数の神社のひとつ。
安蘇澤鎭守にもかかわらず地図に載せてもらえないので探しにくいが,葛生原人発掘跡から見て,道路を挟んで南東方面向かい側の山に鎮座。
目印は正明寺と山菅公民館。この先の山野井採石工業の前。
大正十年十月の御影石明神鳥居。
「常夜燈 安政五午年九月吉日」1858
境内社として記録されている「八坂神社,浅間神社,菅原神社,秋葉神社」のどれか不明だが,拝殿右手の石垣に2社並んでいる。「x納xx三社xx xxxx丁卯」だけ読める石燈籠が2基。
-------------------
本殿:明神造銅版葺 拝殿:入母屋造亜鉛葺 幣殿:切妻造亜鉛葺
例祭:10月19
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
安蘇郡 雷天宮大富士権現 山菅 山菅氏
 |
 |
 |
 |
 |
 |
主祭神:天児屋根命 配神:木花咲耶姫命 境内社:今宮・八坂神社
天正二年1574創建。これを遡ること500年ほど前の治安三年1023九月十九日然生神社(伊耶那岐命),赤城神社,日吉神社を赤城明神と総称して赤石城内に祀った。後に諏訪神社と富士浅間神社を合祀,天正二年に本郷の今宮神社境内に遷宮。この年号を小藤神社創建年としているようだ。この既存の神社に夜泣き石を祀って小富士神社と称した。
これとは別に『下野神社沿革誌』では夜泣き石を祀って小藤明神を創建した説を載せている。
境内に中公民館。
例祭:10月15日
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
安蘇郡 正一位 小藤大明神 中村 村
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-22丁
葛生町大字中字明神山鎭座 村社 小藤神社 祭神天兒屋根命 祭日三月十五日九月九日 氏子百三十五戸 社掌石田茂禱仝村大字仝五八番地住
本社は天正二年1574年正月の創建なり 古老の傳ふる所に因れば其頃藤坂與三といふ人あり或夜此明神山の側りを通行せしに赤兒の啼く聾頻りに聞へければ捨子にてもありなんと开處彼處尋ねしに夫かと思ふものはなけれどたゝ圍り一尺長さ八寸程なる⾭白き石ありて啼聲は全く此より發しゐたり あまりの不思議さに與三此石を神種として小藤明神と祀れり 依て其坂を藤坂峠ともいふよし凡そ宇宙のことに於ける玄妙にして人智の較く判すベからざるものあり 蓋だし理の當に然るべからさる如きものにして事の應さに然るべきものある 猶は小夜の中山夜啼石の人口に膾炙すると同一轍の如きものか暫らく口碑のまヽを記しをく
姓は藤原故に此▢石を神種として其遠祖たね天兒屋根命を祀りたるなり又た藤坂峠といふは本社を東へ距る二丁餘の山坂なり
建物本社本社間口一間奥行一間小羽葺 拜殿間口三間奥行二間瓦葺 幣殿間口二間奥行三間瓦葺 鳥居一基 末社七社
境内地七百七十九坪 社有財產田畝一反三畝八歩山林五反一畝十五歩
明神山は大字の中央にありて田甫の中に屹立せり 高さ五十間餘山の形圓るくして甚だ奇なり 本社は其半腹にありて巌石の山に築れたり 境内は小松生ひ繁りて白沙と相映じ一幅の畫を見る如とし 开は明治二十四年中氏子総代谷孫三郎氏外ー名の奉納にかゝるものなりとそ 其外には樹木多らねど二百餘年を經たらんと覺しき楓及び松杉樫の大木等見るべきものあり 又た眺望に到つては西南人家田甫を隔てヽ小澤山に對し[此山松に富み松茸を産す地方の名産なり]秋山川其間を流る 尚ほ西に谷津山を控ヘ東宮の入山に連り下都賀郡に界す 風光明媚頗る吟笻を曳くの價あり/又た本社を南へ距る田の中に與三墓といへる石碑あり然れども惜むべし其文字は摩滅して明ならず
天正二年1574創建。これを遡ること500年ほど前の治安三年1023九月十九日然生神社(伊耶那岐命),赤城神社,日吉神社を赤城明神と総称して赤石城内に祀った。後に諏訪神社と富士浅間神社を合祀,天正二年に本郷の今宮神社境内に遷宮。この年号を小藤神社創建年としているようだ。この既存の神社に夜泣き石を祀って小富士神社と称した。
これとは別に『下野神社沿革誌』では夜泣き石を祀って小藤明神を創建した説を載せている。
境内に中公民館。
例祭:10月15日
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
安蘇郡 正一位 小藤大明神 中村 村
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-22丁
葛生町大字中字明神山鎭座 村社 小藤神社 祭神天兒屋根命 祭日三月十五日九月九日 氏子百三十五戸 社掌石田茂禱仝村大字仝五八番地住
本社は天正二年1574年正月の創建なり 古老の傳ふる所に因れば其頃藤坂與三といふ人あり或夜此明神山の側りを通行せしに赤兒の啼く聾頻りに聞へければ捨子にてもありなんと开處彼處尋ねしに夫かと思ふものはなけれどたゝ圍り一尺長さ八寸程なる⾭白き石ありて啼聲は全く此より發しゐたり あまりの不思議さに與三此石を神種として小藤明神と祀れり 依て其坂を藤坂峠ともいふよし凡そ宇宙のことに於ける玄妙にして人智の較く判すベからざるものあり 蓋だし理の當に然るべからさる如きものにして事の應さに然るべきものある 猶は小夜の中山夜啼石の人口に膾炙すると同一轍の如きものか暫らく口碑のまヽを記しをく
姓は藤原故に此▢石を神種として其遠祖たね天兒屋根命を祀りたるなり又た藤坂峠といふは本社を東へ距る二丁餘の山坂なり
建物本社本社間口一間奥行一間小羽葺 拜殿間口三間奥行二間瓦葺 幣殿間口二間奥行三間瓦葺 鳥居一基 末社七社
境内地七百七十九坪 社有財產田畝一反三畝八歩山林五反一畝十五歩
明神山は大字の中央にありて田甫の中に屹立せり 高さ五十間餘山の形圓るくして甚だ奇なり 本社は其半腹にありて巌石の山に築れたり 境内は小松生ひ繁りて白沙と相映じ一幅の畫を見る如とし 开は明治二十四年中氏子総代谷孫三郎氏外ー名の奉納にかゝるものなりとそ 其外には樹木多らねど二百餘年を經たらんと覺しき楓及び松杉樫の大木等見るべきものあり 又た眺望に到つては西南人家田甫を隔てヽ小澤山に對し[此山松に富み松茸を産す地方の名産なり]秋山川其間を流る 尚ほ西に谷津山を控ヘ東宮の入山に連り下都賀郡に界す 風光明媚頗る吟笻を曳くの價あり/又た本社を南へ距る田の中に與三墓といへる石碑あり然れども惜むべし其文字は摩滅して明ならず
主祭神:木花咲耶姫命
46坪の境内に権現造の小ぶりの石宮。中沖地区。岩船町小野寺との境辺りの山中か。見つからない。
例祭:10月17日
46坪の境内に権現造の小ぶりの石宮。中沖地区。岩船町小野寺との境辺りの山中か。見つからない。
例祭:10月17日
主祭神:雷大神
小藤神社の北あたりか,小ぶりの石宮だけのようで,見つからない。
例祭:4月15日
小藤神社の北あたりか,小ぶりの石宮だけのようで,見つからない。
例祭:4月15日
主祭神:表筒男命・底筒男命
明治四十二年1909下記の大海神社と会沢の不明社が合併して会澤神社と改称する。昭和四十三年1968現在地に遷宮。
小曽戸は明治九年1876会沢村へ。
例祭:10月第三日曜日 子供神輿渡御
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
安蘇郡 正一位 大海大明神 小曾戸 蓮乗院
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-22丁
葛生町大字會澤字大海鎭座
村社 大海神社 祭神上筒男之命 建物本社間口四尺八寸奥行四尺三寸 拜殿間口壹間半奥行壹間 神輿庫間口一間半奥行二間 祭器庫間口三間奥行一間 氏子百戸 本社勸請詳ならす 社域四百十一坪あり
明治四十二年1909下記の大海神社と会沢の不明社が合併して会澤神社と改称する。昭和四十三年1968現在地に遷宮。
小曽戸は明治九年1876会沢村へ。
例祭:10月第三日曜日 子供神輿渡御
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
安蘇郡 正一位 大海大明神 小曾戸 蓮乗院
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-22丁
葛生町大字會澤字大海鎭座
村社 大海神社 祭神上筒男之命 建物本社間口四尺八寸奥行四尺三寸 拜殿間口壹間半奥行壹間 神輿庫間口一間半奥行二間 祭器庫間口三間奥行一間 氏子百戸 本社勸請詳ならす 社域四百十一坪あり
青木神社
[あおき神社]
栃木県佐野市・会沢
主祭神:猿田彦命
小室は明治九年1876会沢村へ。当社は下記に記録されたが,現在社が分からない。あるいは上記会沢神社になったか?
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
安蘇郡 青木大明神 小室 石川肥後
*『下野掌覧』万延元年1860 安蘇郡之部
青木大明神 小室村鎮座 祭主石川氏ナリ
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-22丁
葛生町大字會澤字沖の澤鎭座 村社 ⾭木神社 祭神猿田彥命 建物 本社間口三尺五寸奥行三尺五寸 拜殿間口一間半奥行一間 氏子二十九戸
本社創立詳ならす 社域百九十八坪あり
小室は明治九年1876会沢村へ。当社は下記に記録されたが,現在社が分からない。あるいは上記会沢神社になったか?
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
安蘇郡 青木大明神 小室 石川肥後
*『下野掌覧』万延元年1860 安蘇郡之部
青木大明神 小室村鎮座 祭主石川氏ナリ
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-22丁
葛生町大字會澤字沖の澤鎭座 村社 ⾭木神社 祭神猿田彥命 建物 本社間口三尺五寸奥行三尺五寸 拜殿間口一間半奥行一間 氏子二十九戸
本社創立詳ならす 社域百九十八坪あり
主祭神:木花咲耶姫命 配神:天津彦火瓊瓊杵命・大山祇命・事代主命・別雷命・軻遇突智命・水波之売命・埴山姫命 境内社:金精大明神・富士浅間大神・秋葉山
弘長二年1262創建と伝わる。境内に良質の石灰岩が埋蔵されていることが分かり,業者が採掘したが粉塵等により荒廃甚だしく昭和四十三年1968葛生字富士山3824より500m西の現在地に遷宮。
例祭:5月1日 子供神輿渡御 神楽舞奉納
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
安蘇郡 富士山大権現 葛生 村樫摂津
*『下野掌覧』万延元年1860 安蘇郡之部
冨士浅間宮 葛生村鎮座 祭主村樫氏ナリ
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-23丁
葛生町大字葛生字村樫鎭座 無格社 淺間神社 祭神木花開郎姫命 祭日陰曆四月初申日 氏子二百三十三戸總代五員 社掌兼務村樫榮次仝村仝大字二百五番地住
惜ひ哉本社の創立年月は詳ならす唯だ舊記に傳ふらく天正十八年徳川家康の覇府を江戸に開くや臣僚榊原式部太夫康政をして上野國邑樂郡舘林に藩鎭たらしむ 康政頓に敬神の志あり本社を崇敬すること常に篤つし事家康に聞へ遂に台命を承けて本宮には富士淺間大神,中宮には粟島大明神,稻荷大神,金精權現,道了權現を併せ祀つり玉垣拜殿,神樂殿,鳥居等をも創建し天正十九年を以て遷宮式を執行す 翌文祿元年八月全く其功を竣り造營の奉行は石川佐治右衛門是を勤めしといふ 其頃奉仕の神主を村樫加賀と稱す 名望一郷に著しき人なり 寛永九年康政の嫡遠江守康勝の嗣子松平式部太夫忠次,安川角之丞,石黑喜左右衛門を以て奉行となし本社中宮修復のことに衝らしめ同五月朔日を以て遷宮の式を行ふ 後承應元1652九月十五日舘林城主松平和泉守乗壽の代に到り奉行内山五兵衛,石田曾兵衛をして再建の事に衝らしむ 今の宮殿は即ち之なりと 要するに本社は世々舘林城の鬼門鎭護の社として崇祀せられたるを以て當時に於ける神の威徳は熾んなる者にて有しなり 明治五年の改正に際し今の祭神に更ためて淺間神社と稱す
建物本社間口一間奥行二間五尺 拜殿間口四間奥行二間五尺 末社五社
境内地三反二畝歩字村樫の中心より南北に當つて蜿蜒山脈の連なる處中に一岡丘の峙つあり之を村樫富士と稱す 頂上は即ち本社のある處なり 宮殿は南に面し馬塲大門は坤向きにして即ち舘林城よりの鬼門に當れり 山上の眺望は田野山嶽尺幅の間に其明媚なる風光を集するを得可く眞に眼界の雄大なるを覺ゆ 境内は松杉樅の類蓊鬱として翠緑滴る如く煩襟頓に消滅す 遠山紫に近水明なるの狀眞に天然の畫圖を爲し薫風松籟を送り來つては身は已てに詩中にあるを感ぜん 若し夫れ玉塵紛々として空林枯木香りふき花を咲かしめ白銀の天地と變じたる暁き試みに此丘陵に對せば蓋だし宛然小芙蓉峰を望むの想あるべし
弘長二年1262創建と伝わる。境内に良質の石灰岩が埋蔵されていることが分かり,業者が採掘したが粉塵等により荒廃甚だしく昭和四十三年1968葛生字富士山3824より500m西の現在地に遷宮。
例祭:5月1日 子供神輿渡御 神楽舞奉納
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
安蘇郡 富士山大権現 葛生 村樫摂津
*『下野掌覧』万延元年1860 安蘇郡之部
冨士浅間宮 葛生村鎮座 祭主村樫氏ナリ
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-23丁
葛生町大字葛生字村樫鎭座 無格社 淺間神社 祭神木花開郎姫命 祭日陰曆四月初申日 氏子二百三十三戸總代五員 社掌兼務村樫榮次仝村仝大字二百五番地住
惜ひ哉本社の創立年月は詳ならす唯だ舊記に傳ふらく天正十八年徳川家康の覇府を江戸に開くや臣僚榊原式部太夫康政をして上野國邑樂郡舘林に藩鎭たらしむ 康政頓に敬神の志あり本社を崇敬すること常に篤つし事家康に聞へ遂に台命を承けて本宮には富士淺間大神,中宮には粟島大明神,稻荷大神,金精權現,道了權現を併せ祀つり玉垣拜殿,神樂殿,鳥居等をも創建し天正十九年を以て遷宮式を執行す 翌文祿元年八月全く其功を竣り造營の奉行は石川佐治右衛門是を勤めしといふ 其頃奉仕の神主を村樫加賀と稱す 名望一郷に著しき人なり 寛永九年康政の嫡遠江守康勝の嗣子松平式部太夫忠次,安川角之丞,石黑喜左右衛門を以て奉行となし本社中宮修復のことに衝らしめ同五月朔日を以て遷宮の式を行ふ 後承應元1652九月十五日舘林城主松平和泉守乗壽の代に到り奉行内山五兵衛,石田曾兵衛をして再建の事に衝らしむ 今の宮殿は即ち之なりと 要するに本社は世々舘林城の鬼門鎭護の社として崇祀せられたるを以て當時に於ける神の威徳は熾んなる者にて有しなり 明治五年の改正に際し今の祭神に更ためて淺間神社と稱す
建物本社間口一間奥行二間五尺 拜殿間口四間奥行二間五尺 末社五社
境内地三反二畝歩字村樫の中心より南北に當つて蜿蜒山脈の連なる處中に一岡丘の峙つあり之を村樫富士と稱す 頂上は即ち本社のある處なり 宮殿は南に面し馬塲大門は坤向きにして即ち舘林城よりの鬼門に當れり 山上の眺望は田野山嶽尺幅の間に其明媚なる風光を集するを得可く眞に眼界の雄大なるを覺ゆ 境内は松杉樅の類蓊鬱として翠緑滴る如く煩襟頓に消滅す 遠山紫に近水明なるの狀眞に天然の畫圖を爲し薫風松籟を送り來つては身は已てに詩中にあるを感ぜん 若し夫れ玉塵紛々として空林枯木香りふき花を咲かしめ白銀の天地と變じたる暁き試みに此丘陵に對せば蓋だし宛然小芙蓉峰を望むの想あるべし
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
主祭神:市杵嶋姫命・厳島大神
築地には井戸が無く山のふもとの清水を用水とした。感謝のため天保五年1834石宮を建てて水神を祀った。本町,倭町,相生町の住民も用水を使用していたので同じく石宮を祀り,合同で祭典を行う。残念ながら磯山の採掘で湧水は枯渇。出流原の磯山弁天とは別の磯山。嘉多山町3871は欠番で現在地が分からない。石宮が三基石垣に乗っている写真があるが。
真南の築地町公民館にある富士浅間神社は氏神さまか。
例祭:4月10日
築地には井戸が無く山のふもとの清水を用水とした。感謝のため天保五年1834石宮を建てて水神を祀った。本町,倭町,相生町の住民も用水を使用していたので同じく石宮を祀り,合同で祭典を行う。残念ながら磯山の採掘で湧水は枯渇。出流原の磯山弁天とは別の磯山。嘉多山町3871は欠番で現在地が分からない。石宮が三基石垣に乗っている写真があるが。
真南の築地町公民館にある富士浅間神社は氏神さまか。
例祭:4月10日
主祭神:大山祇命
昭和六十一年1986遷宮の碑によると「寛政七年1795山菅北山に鎮座したが昭和十年1935五月長坂山の山腹に遷宮。参道は侵食に悩まされ参拝に困難を来していたので,現在地に遷宮」
片山後援の北隣り。もう少し登ると嘉多山稲荷神社と山神が鎮座。
例祭:5月7日
昭和六十一年1986遷宮の碑によると「寛政七年1795山菅北山に鎮座したが昭和十年1935五月長坂山の山腹に遷宮。参道は侵食に悩まされ参拝に困難を来していたので,現在地に遷宮」
片山後援の北隣り。もう少し登ると嘉多山稲荷神社と山神が鎮座。
例祭:5月7日
▊常 磐 村 *『下野神社沿革誌』明治三十五年1902五月十日發行 巻ニ-23丁
本村は仙波,牧,豊代の舊三ヶ村を合せしものにして其面積千七百四十町餘歩にして地勢東北一帶山脉連り北は高原山系あり東に出流連脉あり土地自ら高唆西南の一部平坦にして田圃開くるを見る 南方葛生町と土壌相界し三好村及ひ氷室村は西及ひ西北にありて本村と相接せり 村民一般に農工を業とし勤勉の風あり 道路は一條の假定縣道あり 葛生町より來る其他里道貫通して交通の不便を感ずるに至らす 秋山川は北より南に流る 其他數條の支流ありて用水灌漑の便を之に仰けり
各地往古の沿革に就ては仙波農代の兩村は往時佐野氏の所領たり後ち宗氏の所轄となり牧村は幕府代官の支配する所にして後叉宗氏の所領となり明治維新に際し日光縣に屬し更に栃木縣所轄となり各戸長役塲に分屬せしか町村制實施に當り合併して現時の一村となるに至る 本村には村社三社ありて其氏子戸敷五百三十餘戸人口三千九百三十餘人あり
主祭神:天津兒屋根命 配神:建速素盞嗚命・大鷦鷯命・彦火瓊瓊杵命・大名持命
天慶二年939藤原秀郷が創建。明治四十二年1909六月十四日,秋葉神社,八坂神社,若宮八幡宮,太平神社を合祀。昭和二十一年1946拝殿再建。
例祭:11月23日
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
都賀郡 正一位 今宮大明神 仙波 光明寺
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-24丁
常磐村大字仙波小字伊與鳥屋山鎭座 村社 今宮神社 祭神天津兒屋根命 祭日太陽曆三月廿八日小陰曆十一月十五日 氏子百八十五戸總代五員 社掌天笠範十郎同村大字同五十番地住
社記に曰く天慶二年939平將門叛するや藤原秀郷を以て鎭守府將軍となし兼ねて追討の命を賜ふ 秀郷逆賊鎭滅祈願のため同年十一月十五日を以て本社を創立し丹誠を凝らし身心を抽んで遂に勦戮の功を奏せしかば其子孫に到るまて代々崇敬して奉祀を怠らず遂に佐野修理太夫昌綱の代に及んて同氏大檀那となりて宮殿を修造せり 其頃は二十餘町歩の社領ありて佐野家の總鎭守と稱し又た之を管理する別當職には光明寺なるものありて頗る壯觀を極めしか今は僅かに數反の畑を有するに過きずして坐ろに輪奐の美を盡せし往時を追想せしむるの紀念たる二三の寶物等の存在を認むるかため却て一度本社に詣てし者をして轉た懐舊の情に堪へさらしむ事績已てに斯の如くなれば明治五年社格改正に際し田名網小屋上下仙波牧柿平水ノ木秋山八ヶ村の郷社に定められしか同十年八月の縣令に依つて村社に改定せらる
建物 本社間口六尺奥行五尺 幣殿間口二間奥行一間五尺 拜殿間口二間半奥行二間 雨覆間口二間半奥行三間半 神樂殿間口二間半奥行三間半 寶庫間口八尺奥行九尺 末社十五社 石壁社前長さ十五間高さ一丈二尺なり明治九年1876氏子戸森下▢作の寄進に係る 石燈籠七基 境内地千四百拾坪 境外社有地畑三反五歩其他山林若干あり 寶物 短刀一口長さ九尺五分▢紅錦を以て包む藤原秀郷公の守刀なりしと云ふ 水入瓢一箇/經概ね一尺あり夕顔を似成る/ 神社位記一巻/正徳四年1714従二位卜部朝臣▢筆/大般若六百巻/近衛天皇の久安五年1149願主平忠常の妻藤原氏祈願のため僧快圓に命じ大般若祿百巻を書寫し之を當社に収め元暦元年1184十一月廿三日より慶應年問まて毎年展讀せしめ來りたりや今や冩本は朽敗散減収拾すへからさるに致れり見るへきもの僅に數十巻に過きるを以て寛文十一年1671弘長なるもの願主となり寄附したる板本の大般若經六百巻を之に併せて共に保存せり/古棟札二枚/表に奉上吹今宮大權現とありて裏に大檀那藤原信綱藤原光俊永享三年1431辛亥年八月別當寶生寺大法師榮俊とあり 他の一枝は下野庄仙波奉修別當權少僧都昌俊大檀那藤原憲綱と記しありて裏書には應仁元年1467丁亥二月吉日出流山▢月坊少貳上とあり/
本村里道を入る八十間餘渺漠たる耕地の上に嶄然屹立せるの小丘を見る 之を字伊與鳥屋山と云ふ 本社は即ち其項にあり 五十三段の石階を上りて漸く社頭に逹すへし 又た本社より右の側に當り五十五階の石磴あり 其上に天照大神を祀り嶺の宮といふ 此地北方山嶽を負ひ他の三面は洋々たる田圃にして快濶の氣を吸ふを得へし 加ふるに境内老杉蓊欝枝を參へて天日を洩さす 其幽邃淸雅は地方稀に見る所若し夫翠滴るの朝風淸きの夕此境に遊はヽ登臨一番邪念の頓に散するを覺へむ
江戸時代に常盤村に次の社があったことが記録されている。 *『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
安蘇郡 諏訪大明神 田名綱 村
天慶二年939藤原秀郷が創建。明治四十二年1909六月十四日,秋葉神社,八坂神社,若宮八幡宮,太平神社を合祀。昭和二十一年1946拝殿再建。
例祭:11月23日
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
都賀郡 正一位 今宮大明神 仙波 光明寺
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-24丁
常磐村大字仙波小字伊與鳥屋山鎭座 村社 今宮神社 祭神天津兒屋根命 祭日太陽曆三月廿八日小陰曆十一月十五日 氏子百八十五戸總代五員 社掌天笠範十郎同村大字同五十番地住
社記に曰く天慶二年939平將門叛するや藤原秀郷を以て鎭守府將軍となし兼ねて追討の命を賜ふ 秀郷逆賊鎭滅祈願のため同年十一月十五日を以て本社を創立し丹誠を凝らし身心を抽んで遂に勦戮の功を奏せしかば其子孫に到るまて代々崇敬して奉祀を怠らず遂に佐野修理太夫昌綱の代に及んて同氏大檀那となりて宮殿を修造せり 其頃は二十餘町歩の社領ありて佐野家の總鎭守と稱し又た之を管理する別當職には光明寺なるものありて頗る壯觀を極めしか今は僅かに數反の畑を有するに過きずして坐ろに輪奐の美を盡せし往時を追想せしむるの紀念たる二三の寶物等の存在を認むるかため却て一度本社に詣てし者をして轉た懐舊の情に堪へさらしむ事績已てに斯の如くなれば明治五年社格改正に際し田名網小屋上下仙波牧柿平水ノ木秋山八ヶ村の郷社に定められしか同十年八月の縣令に依つて村社に改定せらる
建物 本社間口六尺奥行五尺 幣殿間口二間奥行一間五尺 拜殿間口二間半奥行二間 雨覆間口二間半奥行三間半 神樂殿間口二間半奥行三間半 寶庫間口八尺奥行九尺 末社十五社 石壁社前長さ十五間高さ一丈二尺なり明治九年1876氏子戸森下▢作の寄進に係る 石燈籠七基 境内地千四百拾坪 境外社有地畑三反五歩其他山林若干あり 寶物 短刀一口長さ九尺五分▢紅錦を以て包む藤原秀郷公の守刀なりしと云ふ 水入瓢一箇/經概ね一尺あり夕顔を似成る/ 神社位記一巻/正徳四年1714従二位卜部朝臣▢筆/大般若六百巻/近衛天皇の久安五年1149願主平忠常の妻藤原氏祈願のため僧快圓に命じ大般若祿百巻を書寫し之を當社に収め元暦元年1184十一月廿三日より慶應年問まて毎年展讀せしめ來りたりや今や冩本は朽敗散減収拾すへからさるに致れり見るへきもの僅に數十巻に過きるを以て寛文十一年1671弘長なるもの願主となり寄附したる板本の大般若經六百巻を之に併せて共に保存せり/古棟札二枚/表に奉上吹今宮大權現とありて裏に大檀那藤原信綱藤原光俊永享三年1431辛亥年八月別當寶生寺大法師榮俊とあり 他の一枝は下野庄仙波奉修別當權少僧都昌俊大檀那藤原憲綱と記しありて裏書には應仁元年1467丁亥二月吉日出流山▢月坊少貳上とあり/
本村里道を入る八十間餘渺漠たる耕地の上に嶄然屹立せるの小丘を見る 之を字伊與鳥屋山と云ふ 本社は即ち其項にあり 五十三段の石階を上りて漸く社頭に逹すへし 又た本社より右の側に當り五十五階の石磴あり 其上に天照大神を祀り嶺の宮といふ 此地北方山嶽を負ひ他の三面は洋々たる田圃にして快濶の氣を吸ふを得へし 加ふるに境内老杉蓊欝枝を參へて天日を洩さす 其幽邃淸雅は地方稀に見る所若し夫翠滴るの朝風淸きの夕此境に遊はヽ登臨一番邪念の頓に散するを覺へむ
江戸時代に常盤村に次の社があったことが記録されている。 *『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
安蘇郡 諏訪大明神 田名綱 村
主祭神:菅原道真朝臣命
創立不詳。大沢騎乗という山伏が船越の政長院で粗末にされていた道真公神像を厨子に入れて運んできて成就院に数年安置した後,現在地に祠を建てて祀った。弘化四年1847「大澤山天神」掛軸。
令和三年900m北の上記今宮神社と合併し,境内社となる。
例祭:11月23日
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
都賀郡 大沢天神宮 仙波 村民
創立不詳。大沢騎乗という山伏が船越の政長院で粗末にされていた道真公神像を厨子に入れて運んできて成就院に数年安置した後,現在地に祠を建てて祀った。弘化四年1847「大澤山天神」掛軸。
令和三年900m北の上記今宮神社と合併し,境内社となる。
例祭:11月23日
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
都賀郡 大沢天神宮 仙波 村民
主祭神:田原又太郎忠綱・戸屋子七郎有綱・小野寺前目太郎道綱 配神:武甕槌命・級長津彦命・級長津姫命
祭神は戦に敗れ落ち延びて当地で亡くなった三人の武将と伝わり(『栃木県神社誌』平成18年版),三騎の根拠になっている。しかし道綱は承久の乱で勝利するも宇治川で討ち死にし,首は故郷の岩船小野寺に持ち帰られたとの説が有力。戸矢子有綱は佐野の石室で自害。場所は戸矢子の戸と石室から戸室の地名となる。忠綱の死亡地は上野国。三人とも由緒とは異なる。
鳥居額はとても「三騎」とは読めない。「神」も浅学にはとても無理。騎も奇も崩し字であてはまらない書体。「三定」がいちぱん近いが,「三宮」が適当だろう。江戸期の下記の資料では「三崎」「三嵜」の表記なので,騎馬武者の「騎」ではなかったかもしれない。明治以降の額らしいので配神の三神から額文字は「三宮」かもしれない。明治四十年「三宮合社之碑」に「謂三宮祭式之座」とあるので。碑の三の字は説文由来。「三騎明神」のくだりは肝腎のところが読めない。
なかなかに謎の多い社である。
明治四十年1907岩崎の鹿島神社(武甕槌命),根渡神社(志那都彦命・志那都姫命)を合祀。石鳥居を建立。
昭和四年1929焼失するも翌年再建。
船越町2828に極彩色の三騎神社(天津兒屋根命)が鎭座する。
例祭:4月29日
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
都賀郡 正一位 三崎大明神 岳崎 森伊勢 仙波は明治9年までは都賀郡
*『下野掌覧』万延元年1860 安蘇郡之部
正一位 三嵜大明神 岩嵜村鎮座 祭主森氏ナリ
祭神は戦に敗れ落ち延びて当地で亡くなった三人の武将と伝わり(『栃木県神社誌』平成18年版),三騎の根拠になっている。しかし道綱は承久の乱で勝利するも宇治川で討ち死にし,首は故郷の岩船小野寺に持ち帰られたとの説が有力。戸矢子有綱は佐野の石室で自害。場所は戸矢子の戸と石室から戸室の地名となる。忠綱の死亡地は上野国。三人とも由緒とは異なる。
鳥居額はとても「三騎」とは読めない。「神」も浅学にはとても無理。騎も奇も崩し字であてはまらない書体。「三定」がいちぱん近いが,「三宮」が適当だろう。江戸期の下記の資料では「三崎」「三嵜」の表記なので,騎馬武者の「騎」ではなかったかもしれない。明治以降の額らしいので配神の三神から額文字は「三宮」かもしれない。明治四十年「三宮合社之碑」に「謂三宮祭式之座」とあるので。碑の三の字は説文由来。「三騎明神」のくだりは肝腎のところが読めない。
なかなかに謎の多い社である。
明治四十年1907岩崎の鹿島神社(武甕槌命),根渡神社(志那都彦命・志那都姫命)を合祀。石鳥居を建立。
昭和四年1929焼失するも翌年再建。
船越町2828に極彩色の三騎神社(天津兒屋根命)が鎭座する。
例祭:4月29日
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
都賀郡 正一位 三崎大明神 岳崎 森伊勢 仙波は明治9年までは都賀郡
*『下野掌覧』万延元年1860 安蘇郡之部
正一位 三嵜大明神 岩嵜村鎮座 祭主森氏ナリ
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
主祭神:菅原道真朝臣命 配神:大雷命・天照皇大神・大山祇命・伊耶那岐命・素盞嗚命・木花咲耶姫命
貞和(北朝)二年1346創建。正保年間1644~48に天神山から現在地に遷宮。菅原道真公神社と称した。拝殿に「菅原神社」額が残っている。
明治四十二年1909五月二十四日,字九通雷電神社,字九通神明宮,字明通山神社,字明通熊野神社,字治通産泰神社,八坂神社,字治通唐渡天満宮(牧町531に現存)を合祀して常磐神社と改称。「記念」碑には「明治四十四年1911十一月廿七日合併」とある。
例祭:11月25日
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
安蘇郡 天満宮 小屋
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-25丁
常磐村大字牧字九通鎭座 村社 菅原神社 祭神菅原道眞靈 建物 本社間口三尺二寸奥行二尺八寸栃葺 拜殿間口二間半奥行二間 雨覆間口二間半奥行二間 雑含一棟 木鳥居一基 氏子二百三十二戸 社掌小松原仙三郎仝村大字豊代一一三番地住
本社は貞和二年1346九月廿八日の創立佐野越前守成綱の勸請にして筑紫大宰府安樂寺より奉遷すと云ふ 社域二百三十二坪を有す 往古は天神山の中腹に在りしを正保年中今の地に移遷し今は該山の東麓に位し東に向ひ前は田圃を隔て秋山の淸流滾々として耳を洗ふに足る 境内には古杉老槻/一丈八尺回り/櫻等ありて頗る幽邃にして雅致あり
唐渡天満宮
貞和(北朝)二年1346創建。正保年間1644~48に天神山から現在地に遷宮。菅原道真公神社と称した。拝殿に「菅原神社」額が残っている。
明治四十二年1909五月二十四日,字九通雷電神社,字九通神明宮,字明通山神社,字明通熊野神社,字治通産泰神社,八坂神社,字治通唐渡天満宮(牧町531に現存)を合祀して常磐神社と改称。「記念」碑には「明治四十四年1911十一月廿七日合併」とある。
例祭:11月25日
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
安蘇郡 天満宮 小屋
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-25丁
常磐村大字牧字九通鎭座 村社 菅原神社 祭神菅原道眞靈 建物 本社間口三尺二寸奥行二尺八寸栃葺 拜殿間口二間半奥行二間 雨覆間口二間半奥行二間 雑含一棟 木鳥居一基 氏子二百三十二戸 社掌小松原仙三郎仝村大字豊代一一三番地住
本社は貞和二年1346九月廿八日の創立佐野越前守成綱の勸請にして筑紫大宰府安樂寺より奉遷すと云ふ 社域二百三十二坪を有す 往古は天神山の中腹に在りしを正保年中今の地に移遷し今は該山の東麓に位し東に向ひ前は田圃を隔て秋山の淸流滾々として耳を洗ふに足る 境内には古杉老槻/一丈八尺回り/櫻等ありて頗る幽邃にして雅致あり
唐渡天満宮
東宮神社
[とうぐう神社]
栃木県佐野市・牧町1871←葛生町大字牧
主祭神:建御名方命・譽田別命 境内社:厳島神社・山神社・神明神社・神明宮・八幡神社・駒形神社
元永二年1119創建,東宮大明神と称した。大永三年1523長島藤三郎行房が再建,諏訪八幡宮と改称。享保十年1725以降数度の遷宮。明治四十二年1909六社を合祀し境内社とする。このとき東宮神社と改称。2021年現在社殿倒壊のまま。
旗杭脇に大きな庚申塔。
昭和三十年1955常磐村から葛生町に変更。
例祭:11月25日
旗杭脇に大きな庚申塔。
昭和三十年1955常磐村から葛生町に変更。
例祭:11月25日
浅間大神神社
[せんげんおおかみ神社]
栃木県佐野市・牧町2337-1←葛生町牧年通り
主祭神:木花咲耶姫命 配神:大山祇命・磐長姫命
昭和三十年1955常磐村から葛生町に変更。
明治四十年1907八月,牧3330にあった石尊神社(大山祇命・磐長姫命)を合祀。
サンモリッツの中か?
例祭:8月1日
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
都賀郡 八竜浅間大明神 牧 広瀬氏
*『下野掌覧』万延元年1860 安蘇郡之部
八龍浅間大明神 牧村鎮座 祭主廣瀬氏ナリ
昭和三十年1955常磐村から葛生町に変更。
明治四十年1907八月,牧3330にあった石尊神社(大山祇命・磐長姫命)を合祀。
サンモリッツの中か?
例祭:8月1日
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
都賀郡 八竜浅間大明神 牧 広瀬氏
*『下野掌覧』万延元年1860 安蘇郡之部
八龍浅間大明神 牧村鎮座 祭主廣瀬氏ナリ
箱石神社
[はこいし神社]
栃木県佐野市・豊代町252

主祭神:譽田別命 配神:豊受姫命・大彦命・武渟川別命・吉備津彦命・大山祇命
延文(北朝)元年1356戸叶孫右衛門が創建。昭和四十年1965境内の松檜を伐採して拝殿を新改築。
例祭:11月23日
延文(北朝)元年1356戸叶孫右衛門が創建。昭和四十年1965境内の松檜を伐採して拝殿を新改築。
例祭:11月23日
主祭神:菅原道真朝臣命
長禄二年1458創建。秋山川右岸,最勝院の南隣りに鎭座。
例祭:4月29日 弓引行事
長禄二年1458創建。秋山川右岸,最勝院の南隣りに鎭座。
例祭:4月29日 弓引行事
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
主祭神:月読命
創立年等不詳。昭和四十年1965拝殿改築。小屋町鎮守。
例祭:1月3日
創立年等不詳。昭和四十年1965拝殿改築。小屋町鎮守。
例祭:1月3日
▊氷室村 *『下野神社沿革誌』明治三十五年1902五月十日發行 巻ニ-26丁
本村は柿平,秋山及ひ水木の舊三村を合して一自治區と爲せしものにして全村の面積千五百二十餘町歩に逹せり 地勢高陵にして山嶽多く平地少にして東北は一帶の山脉連亘して境界を限り氷室山十二岳等此間に聳立して上都賀及ひ上野の勢多郡と界し西は野上村に隣し漸く土地の開くるを見る 南は常磐村と相接せり 本村郡内は山丘の多き地にして高山も亦實に此地に在り 村民は農耕を専務とし木材薪炭業に従事するもの亦多し 縣道は秋山水木を通し葛生町に逹すヘく其他幾線の里道なきに非さるも山間の地方にて交通の便多少欠くるものなきに非さるなり 秋山川は本村氷室山より發す 本村此川により用水路を開き灌漑に供す
古來の沿革に就ては各村共往時本多上野介の所領たりしか后幕府代官の領する所となり后又幾多の領主を代へしか明治維新の后日光縣の管轄となり次て栃木縣に屬し同一戸長役塲の支配となり更に町村制實施に當り合併して一村とはなりぬ
本村には村社三社及ひ有名の無格社氷室山神社外一社あり 其氏子戸數三百餘戸人口二千四百四十餘人あり
富俵山神社
[ふたわらやま神社]
栃木県佐野市・柿平町392
主祭神:大名持命・事代主命・田心姫命 配神:武甕槌命・少彦名命・素盞嗚命・月読命・軻遇突智命
明治四十年1907四月,柿平の鹿島神社,温泉神社,八坂神社を合祀,祭神を配神とする。
二荒山の縁起のいい字で富俵山だと推測する。『栃木県神社誌』平成18年版のルビは[とみたわらやま]だが,旧版では[ふたわらやま]。
例祭:5月3日
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-26丁
氷室村大字柿平北之内鎭座 村社 富俵神社 祭神大名持命 味耜高彥根命 田心姫命 祭日陰曆三月三十日九月十五日 建物本社白木惣彫惣槻造高一丈餘 幣殿間口一間奥行二間 雨覆間口二間奥行二間 拜殿間口五間奥行二間萱葺 末社二社 木鳥居一基 氏子百戸總代三員 社掌田濤仙郎仝村大字仝十三番地住
本社の創立年月詳かならずと雖も文久三年1863白川伯王殿の勸遷にて正一位の宣旨を授けられ共に神號の扁額を下し賜りて今尚存せり 維新の際村社に列せらる 社境は里道の西側にあり 社域三百七坪高燥の地にして石磴十二階登りて拜殿に逹す 境内には梅櫻常磐木交接して相連る 殊に槻の老樹ありて神々しく感せらる
次の温泉神社は明治四十年1907四月三日,鹿島神社,八坂神社と合併して富俵山神社と改称。
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-28丁
氷室村大字柿平小字湯谷鎭座 無格社 温泉神社 祭神武甕槌命 少彥名命 祭日陰曆四月一日九月十九日 建物本社白木惣彫惣槻造高一丈餘 雨覆間口二間奥行二間 拜殿間口五間奥行二間萱葺 木鳥居一基 末社六社 氏子信徒六十三戸總代三員 社掌田濤仙郎仝村大字仝十三番地住
社傳に曰く當社は往古湯谷權現と稱す 又此社地をも湯谷と稱へ温泉涌出せし所にして縁記にも古昔温泉ありて浴客群集せり中古天正年間浮浪の徒此社地に屯集し温泉に浴するを名とし叛を謀る事上聞に逹し當國唐澤山の城主佐野氏命を蒙り征討の際鮮血淋漓として社地及泉原を瀆せしにより忽ち温泉變して冷泉となると 緑記及古老の口碑に傳ふる處なり 然とも今尚浴客群集益々年に月に盛んなり 社域六百三十一坪にして後ろに高山を負ひ山端に位せる丘陵にて六十七階の石磴を踏みて本殿に逹す 境内には古杉老樹森々蓊蔚として繁茂し春は梅櫻馥郁と薫香を發し初夏の如きは藤色爛漫樹上に蟠垂し秋季は滿山の紅葉本社を輝し其眺望實に言語に盡し難し實に山水明美の佳境なり
因に曰ふ本社再建の際明治廿二年五月氏子村民等が本社の神徳を不朽に残さんとて本社の由緒及古老の口碑等を録して一大碑を社側に建設せり
柿平には200年以上前に2社記録されているが,現在社は分からない。
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
安蘇郡 塩釜大明神 柿平 湯屋源介
安蘇郡 慈現大明神 上柿平
明治四十年1907四月,柿平の鹿島神社,温泉神社,八坂神社を合祀,祭神を配神とする。
二荒山の縁起のいい字で富俵山だと推測する。『栃木県神社誌』平成18年版のルビは[とみたわらやま]だが,旧版では[ふたわらやま]。
例祭:5月3日
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-26丁
氷室村大字柿平北之内鎭座 村社 富俵神社 祭神大名持命 味耜高彥根命 田心姫命 祭日陰曆三月三十日九月十五日 建物本社白木惣彫惣槻造高一丈餘 幣殿間口一間奥行二間 雨覆間口二間奥行二間 拜殿間口五間奥行二間萱葺 末社二社 木鳥居一基 氏子百戸總代三員 社掌田濤仙郎仝村大字仝十三番地住
本社の創立年月詳かならずと雖も文久三年1863白川伯王殿の勸遷にて正一位の宣旨を授けられ共に神號の扁額を下し賜りて今尚存せり 維新の際村社に列せらる 社境は里道の西側にあり 社域三百七坪高燥の地にして石磴十二階登りて拜殿に逹す 境内には梅櫻常磐木交接して相連る 殊に槻の老樹ありて神々しく感せらる
次の温泉神社は明治四十年1907四月三日,鹿島神社,八坂神社と合併して富俵山神社と改称。
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-28丁
氷室村大字柿平小字湯谷鎭座 無格社 温泉神社 祭神武甕槌命 少彥名命 祭日陰曆四月一日九月十九日 建物本社白木惣彫惣槻造高一丈餘 雨覆間口二間奥行二間 拜殿間口五間奥行二間萱葺 木鳥居一基 末社六社 氏子信徒六十三戸總代三員 社掌田濤仙郎仝村大字仝十三番地住
社傳に曰く當社は往古湯谷權現と稱す 又此社地をも湯谷と稱へ温泉涌出せし所にして縁記にも古昔温泉ありて浴客群集せり中古天正年間浮浪の徒此社地に屯集し温泉に浴するを名とし叛を謀る事上聞に逹し當國唐澤山の城主佐野氏命を蒙り征討の際鮮血淋漓として社地及泉原を瀆せしにより忽ち温泉變して冷泉となると 緑記及古老の口碑に傳ふる處なり 然とも今尚浴客群集益々年に月に盛んなり 社域六百三十一坪にして後ろに高山を負ひ山端に位せる丘陵にて六十七階の石磴を踏みて本殿に逹す 境内には古杉老樹森々蓊蔚として繁茂し春は梅櫻馥郁と薫香を發し初夏の如きは藤色爛漫樹上に蟠垂し秋季は滿山の紅葉本社を輝し其眺望實に言語に盡し難し實に山水明美の佳境なり
因に曰ふ本社再建の際明治廿二年五月氏子村民等が本社の神徳を不朽に残さんとて本社の由緒及古老の口碑等を録して一大碑を社側に建設せり
柿平には200年以上前に2社記録されているが,現在社は分からない。
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
安蘇郡 塩釜大明神 柿平 湯屋源介
安蘇郡 慈現大明神 上柿平
鹿島神社
[かしま神社]
栃木県佐野市・水木町664

旧地名:安蘇郡・葛生町大字水木岩沢664/安蘇郡・氷室村大字水木字岩澤
主祭神:武甕槌命 配神:菅原道真朝臣命・天津古屋根命
仙波を抜け県道283号線から続く山道を下りて行くと県道200号線に入る。その手前の氷室の集落上に鎮座。
拝殿左手の道沿いに招魂社の石祠。
鹿嶋神社から秋山川をさかのぼると秋山川源流大滝に行ける。さらに進むと思川上流の山の神バンガローに出る。下って行くと発光路経由で粕尾に出る。
創建年等不詳。明治四十年1907十月水木の天満宮,今宮神社(天津古屋根命)を合祀。
例祭:11月3日
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
安蘇郡 鹿島大明神 水野木 広瀬氏
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-27丁
氷室村大字水木字岩澤鎭座 村社 鹿嶋社 祭神武甕槌神 建物本社間口二間奥行一間半 拜殿間口五間奥行二間 末社三社 氏子六十八戸総代-員 社掌田濤仙郎仝村大字柿平住
本社創立詳かならす 社域六百三十坪を有す
主祭神:武甕槌命 配神:菅原道真朝臣命・天津古屋根命
仙波を抜け県道283号線から続く山道を下りて行くと県道200号線に入る。その手前の氷室の集落上に鎮座。
拝殿左手の道沿いに招魂社の石祠。
鹿嶋神社から秋山川をさかのぼると秋山川源流大滝に行ける。さらに進むと思川上流の山の神バンガローに出る。下って行くと発光路経由で粕尾に出る。
創建年等不詳。明治四十年1907十月水木の天満宮,今宮神社(天津古屋根命)を合祀。
例祭:11月3日
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
安蘇郡 鹿島大明神 水野木 広瀬氏
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-27丁
氷室村大字水木字岩澤鎭座 村社 鹿嶋社 祭神武甕槌神 建物本社間口二間奥行一間半 拜殿間口五間奥行二間 末社三社 氏子六十八戸総代-員 社掌田濤仙郎仝村大字柿平住
本社創立詳かならす 社域六百三十坪を有す
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 拝殿裏手 | ||
 |
 |
 |
| 招魂社 | 招魂社の文字 | |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 秋山川源流 | ||
 |
 |
|
| 山の神に向かう途中に大山祇神社 | 昭和53年の社柱は「大山祇命」 |
主祭神:建御名方命 配神:大山祇命・武甕槌命・素盞嗚命?
『栃木県神社誌』昭和39年版,平成18年版では同文で,至徳(北朝)元年1384創建。明治四十二年1909四月,山神社,八坂?神社,鹿島神社を合祀,梅木鹿島神社(『鹿沼聞書・下野神名帳』に記録されている)跡地に奉祭して氷室山神社と改称とされる。
しかし『下野神社沿革誌』では仁和元年885創建で別の縁起を伝える。昭和五十一年1976拝殿改築碑に沿革誌記載の江戸大火の件が刻まれている。
また碑文では合祀社は八坂神社ではなく諏訪神社となっている。すると秋山字諏訪に記録された諏訪神社で整合性がとれる。諏訪神社の建御名方命を氷室山神社の主祭神にしたことになる。
例祭:11月3日
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
安蘇郡 正一位 鹿島大明神 梅木 菅原隼人
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-27丁
氷室村大字秋山小字氷室鎭座 無格社 氷室神社 祭神大山祇命 祭日三月七日十月七日 氏子百五十戸總代七員 社掌萱原重安同村同大字三十六番地住
本社は元と安賀部山神と稱し安蘇郡の北隅安蘇川の水源なる字氷室に鎭座せしものにて人皇五十九代宇多天皇の御宇仁和元年885秋山村開闢の時勸請せしものなりと傳ふ 其後天保五年1834江戸に大火あり當時領主宗對馬守の舘已てに危ふく見へければ不取敢領地内なる安賀部山神へ火難退除の祈願をなし精神を罩めて三度拜伏するや否や其誠神に通ぜしと見へ何人の手にも餘りしさしもの大火も鎭まりて無難なりしを以て感喜に堪へず是れか禮意を表せんため對馬守は遥る上京して大に本社のために盡す處ありたりといふ 元とより其頃の事なれば九重の雲深く鎖ざし禁廷の摸様などは知るに由しなしと雖も夫れかあらぬか果せる哉遂に帝の叡聞に逹せしと見へ弘化四年十二月十七日を以て正一位氷室山神との勅宣を下し給ふ 畏しと申すも中々に愚なり/今ま其寫しを得たれと絛々しけれは載せず/其他に種々の事績あれ共姑らく之を畧す
建物 本社間口十尺奥行十尺板葺 拜殿間口五間半奥行二間半 寶庫間口九間奥行二間 雑舎四棟 境内地千五百坪 寶物不見引幕一張猩々火地に聞く柄を金にて縫ふ領主宗對馬守の奉納に係る 御神酒器一組松平加賀守より國産九谷焼を奉納せし也 太刀一本有馬玄蕃頭殿の奉納にて無銘なり 小太刀一本奉納は井伊掃部頭にして亂れ焼きなり 外に種々あれども畧す
本社は大字秋山に峨々として霄漢を磨するの高峰あり之を氷室山となす 本社は即ち其項に鎭座す 眸を放つて四邊を眺望すれは東に筑波加波足尾の諸山を臨み大瀧百川の釜淵等は袵席の下に點々指顧すヘし 西は赤城の脈を隔て淺間山に對すべく北に日光中禪寺足尾銅山那須嶽磐梯山を望むべし若し夫れ南方視線の極まる所に至つては東京横濱は勿論豆州熱海の風光を眼中に牧むるを得べし 亦た是塵懐を脱するの別境なり
明治中期に秋山に諏訪神社が記録されているが現在社は分からない。
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
安蘇郡 正一位 諏訪大明神 秋山 菅原隼人
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-27丁
氷室村大字秋山字諏訪鎭座 村祉 諏訪神社 祭神健御名方命 建物本社間口五尺奥行七尺 拜殿間口五間一尺奥行三間 末社三社 華表一基 氏子百四十戸總代七員 社掌萱原重安仝村仝大字三十六番地住
本社創立年月詳ならすと雖も往古より一村の產土神にして大字秋山の東端に位し社域三百廿三坪高燥の地にして古杉老檜蓊蔚として深邃なり
『栃木県神社誌』昭和39年版,平成18年版では同文で,至徳(北朝)元年1384創建。明治四十二年1909四月,山神社,八坂?神社,鹿島神社を合祀,梅木鹿島神社(『鹿沼聞書・下野神名帳』に記録されている)跡地に奉祭して氷室山神社と改称とされる。
しかし『下野神社沿革誌』では仁和元年885創建で別の縁起を伝える。昭和五十一年1976拝殿改築碑に沿革誌記載の江戸大火の件が刻まれている。
また碑文では合祀社は八坂神社ではなく諏訪神社となっている。すると秋山字諏訪に記録された諏訪神社で整合性がとれる。諏訪神社の建御名方命を氷室山神社の主祭神にしたことになる。
例祭:11月3日
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
安蘇郡 正一位 鹿島大明神 梅木 菅原隼人
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-27丁
氷室村大字秋山小字氷室鎭座 無格社 氷室神社 祭神大山祇命 祭日三月七日十月七日 氏子百五十戸總代七員 社掌萱原重安同村同大字三十六番地住
本社は元と安賀部山神と稱し安蘇郡の北隅安蘇川の水源なる字氷室に鎭座せしものにて人皇五十九代宇多天皇の御宇仁和元年885秋山村開闢の時勸請せしものなりと傳ふ 其後天保五年1834江戸に大火あり當時領主宗對馬守の舘已てに危ふく見へければ不取敢領地内なる安賀部山神へ火難退除の祈願をなし精神を罩めて三度拜伏するや否や其誠神に通ぜしと見へ何人の手にも餘りしさしもの大火も鎭まりて無難なりしを以て感喜に堪へず是れか禮意を表せんため對馬守は遥る上京して大に本社のために盡す處ありたりといふ 元とより其頃の事なれば九重の雲深く鎖ざし禁廷の摸様などは知るに由しなしと雖も夫れかあらぬか果せる哉遂に帝の叡聞に逹せしと見へ弘化四年十二月十七日を以て正一位氷室山神との勅宣を下し給ふ 畏しと申すも中々に愚なり/今ま其寫しを得たれと絛々しけれは載せず/其他に種々の事績あれ共姑らく之を畧す
建物 本社間口十尺奥行十尺板葺 拜殿間口五間半奥行二間半 寶庫間口九間奥行二間 雑舎四棟 境内地千五百坪 寶物不見引幕一張猩々火地に聞く柄を金にて縫ふ領主宗對馬守の奉納に係る 御神酒器一組松平加賀守より國産九谷焼を奉納せし也 太刀一本有馬玄蕃頭殿の奉納にて無銘なり 小太刀一本奉納は井伊掃部頭にして亂れ焼きなり 外に種々あれども畧す
本社は大字秋山に峨々として霄漢を磨するの高峰あり之を氷室山となす 本社は即ち其項に鎭座す 眸を放つて四邊を眺望すれは東に筑波加波足尾の諸山を臨み大瀧百川の釜淵等は袵席の下に點々指顧すヘし 西は赤城の脈を隔て淺間山に對すべく北に日光中禪寺足尾銅山那須嶽磐梯山を望むべし若し夫れ南方視線の極まる所に至つては東京横濱は勿論豆州熱海の風光を眼中に牧むるを得べし 亦た是塵懐を脱するの別境なり
明治中期に秋山に諏訪神社が記録されているが現在社は分からない。
*『鹿沼聞書・下野神名帳』1800年頃
安蘇郡 正一位 諏訪大明神 秋山 菅原隼人
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902 巻ニ-27丁
氷室村大字秋山字諏訪鎭座 村祉 諏訪神社 祭神健御名方命 建物本社間口五尺奥行七尺 拜殿間口五間一尺奥行三間 末社三社 華表一基 氏子百四十戸總代七員 社掌萱原重安仝村仝大字三十六番地住
本社創立年月詳ならすと雖も往古より一村の產土神にして大字秋山の東端に位し社域三百廿三坪高燥の地にして古杉老檜蓊蔚として深邃なり
山神社
[さん神社]
栃木県佐野市・長坂町4033←大字葛生4033
主祭神:大山祇命
由緒等分からないが,『栃木県神社誌』昭和39年版に崇敬者が3000人,境内地2550坪とある。新版には非掲載。セメント鳥居,本殿と昔の本殿の記録が残っている。
葛生は複雑に町名変更があって旧住所の対照表が見つからないので市役所に行かないと確定できない。Webに対照表を公開して欲しい。
210号線東の長坂の山の上でいいと思うのだが確定できない。
例祭:5月7日
由緒等分からないが,『栃木県神社誌』昭和39年版に崇敬者が3000人,境内地2550坪とある。新版には非掲載。セメント鳥居,本殿と昔の本殿の記録が残っている。
葛生は複雑に町名変更があって旧住所の対照表が見つからないので市役所に行かないと確定できない。Webに対照表を公開して欲しい。
210号線東の長坂の山の上でいいと思うのだが確定できない。
例祭:5月7日
主祭神:大山祇命 配神:水波之女命(罔象女神)・須佐之男命・勝速日命 境内社:天満宮
永享六年1434創建。元禄二年1689再建。
明治四十二年1909九月,八坂神社,境内にあった麻多利神社を合祀。大正十一年1922三月,水神社を合祀。
例祭:10月第二日曜日
永享六年1434創建。元禄二年1689再建。
明治四十二年1909九月,八坂神社,境内にあった麻多利神社を合祀。大正十一年1922三月,水神社を合祀。
例祭:10月第二日曜日
▊葛生町
*『下野神社沿革誌』明治三十五年1902五月十日發行 巻ニ-19丁
本町は舊葛生,中,會澤及ひ山菅の一宿三村を合併して一の自治區をなせしものにして南方田沼町と相接し往來頗る頻繁にして近來一市衆をなすの觀なきに非す 地勢東方は出流山系連亘し來りて山脉起伏し田沼に走りて唐澤山系となり土地自ら高崇なり 西は三好村に接し北は常磐村と界し其間耕地開け居るを見る 町民は農商工にして葛生は商工多く殊に有名なる石灰產地なり 其他は多く農業を營めり 各地の風俗概して敦厚にして勵精勤勉し交際親密なり 又道路交通の便に至りては田沼町に劣るも非す四通八逹にして縣道は栃木より來り田沼より集中し各地に走り里道亦此間に連絡し頗る便あり 加ふるに佐野鐵道開通以來交通の利一層の利を加へ従て產業發逹等近來大に見るへきものあり 秋山川は町の西方を流れ南下し其他幾多の支流細川ありて頗る用水に便なりと云ふ
古來の沿革に付ては各地共徃時佐野氏の累代領する所たりしか後葛生,會澤,中等は宇都宮本多家の所領となり更に舘林城主の領地となり次て幕府代官の知行所となりしか明治維新の後に至り共に栃木縣に屬し一戸長役塲の所轄となり次て町村制實施に至り舊町村分合の結果之を合併して一町となし葛生町と稱す
本町には郷社一社村社五社及ひ有名の無格社一社ありて其氏子戸數八百餘戸人口五千五百四十餘人あり
本町は舊葛生,中,會澤及ひ山菅の一宿三村を合併して一の自治區をなせしものにして南方田沼町と相接し往來頗る頻繁にして近來一市衆をなすの觀なきに非す 地勢東方は出流山系連亘し來りて山脉起伏し田沼に走りて唐澤山系となり土地自ら高崇なり 西は三好村に接し北は常磐村と界し其間耕地開け居るを見る 町民は農商工にして葛生は商工多く殊に有名なる石灰產地なり 其他は多く農業を營めり 各地の風俗概して敦厚にして勵精勤勉し交際親密なり 又道路交通の便に至りては田沼町に劣るも非す四通八逹にして縣道は栃木より來り田沼より集中し各地に走り里道亦此間に連絡し頗る便あり 加ふるに佐野鐵道開通以來交通の利一層の利を加へ従て產業發逹等近來大に見るへきものあり 秋山川は町の西方を流れ南下し其他幾多の支流細川ありて頗る用水に便なりと云ふ
古來の沿革に付ては各地共徃時佐野氏の累代領する所たりしか後葛生,會澤,中等は宇都宮本多家の所領となり更に舘林城主の領地となり次て幕府代官の知行所となりしか明治維新の後に至り共に栃木縣に屬し一戸長役塲の所轄となり次て町村制實施に至り舊町村分合の結果之を合併して一町となし葛生町と稱す
本町には郷社一社村社五社及ひ有名の無格社一社ありて其氏子戸數八百餘戸人口五千五百四十餘人あり



